相続、それは大切な方が遺してくれた財産と想いを引き継ぐ人生の大きな節目です。中でも、預貯金や有価証券は、日々の暮らしに深く関わる身近な財産でありながら、いざ相続となると「何から始めればいいの?」「どんな書類が必要?」「どこに相談すればいいの?」と、その手続きの複雑さに戸惑う方が少なくありません。
この記事では、相続手続きの中でも特に「預貯金」と「有価証券」に焦点を当て、その全体像から具体的なステップ、必要書類、注意点までを、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、預貯金や有価証券の相続手続きの全体フローを理解し、スムーズに手続きを進めるための具体的なアクションが明確になります。もう、手続きの複雑さに頭を抱える必要はありません。
相続は、故人との絆を感じながら、次世代へ財産と想いを繋いでいく大切なプロセスです。この記事が、そのプロセスを円滑に進めるための一助となれば幸いです。
相続手続きの第一歩:何から始めるべきか?
預貯金や有価証券の相続手続きは、相続手続き全体のプロセスの一部として進められます。まずは、相続が発生してから最初に行うべきことから確認しましょう。
1. 死亡の確認と関係者への連絡
相続は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点から開始します。まずは医師による死亡確認を受け、死亡診断書(死体検案書)を取得します。これはその後の様々な手続きで必要となる非常に重要な書類です。
その後、親族や関係者に訃報を伝えます。同時に、遺言書の有無や相続に関する話し合いのため、相続人となる可能性のある人たちに連絡を取ることが一般的です。
2. 遺言書の確認・有無の調査
被相続人が遺言書を作成していたかどうかを確認することは非常に重要です。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産を分割することになります。
遺言書の主な種類と確認方法
- 自筆証書遺言: 被相続人が自分で書き、押印した遺言書です。自宅や貸金庫に保管されていることがあります。2020年7月10日からは法務局での保管制度も始まりました。法務局に問い合わせることで確認できます。
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人が作成する遺言書です。公証役場に問い合わせることで、全国の公証役場で作成された公正証書遺言の有無を検索できます。
- 秘密証書遺言: 遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけを証明してもらう遺言書です。
自宅などで自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります(法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)。検認を経ずに開封・執行した場合、過料の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
遺言書が見つからない場合や、見つかった遺言書が無効な場合は、法定相続分または遺産分割協議によって遺産を分割することになります。
3. 相続人の確定(戸籍謄本収集)
相続手続きを進める上で、誰が相続人であるかを正確に確定することは非常に重要です。これは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得することで行います。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本に加え、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
この戸籍謄本の収集は、相続関係が複雑な場合(再婚、養子縁組など)には多くの時間と労力を要することがあります。収集した戸籍謄本等をもとに「相続関係説明図」を作成すると、その後の手続きがスムーズに進みます。
預貯金・有価証券の相続手続きフロー全体像
相続人と遺言書の有無が確定したら、いよいよ具体的な財産調査と手続きに入ります。預貯金と有価証券の相続手続きは、以下の流れで進むのが一般的です。
- 相続財産の調査・評価
- 金融機関・証券会社への連絡と一時停止
- 必要書類の準備・提出
- 名義変更または解約・払い戻し
- (必要に応じて)相続税の申告・納付
各ステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:相続財産の調査・評価
被相続人がどの金融機関に口座を持っていたか、どのような有価証券を保有していたかを調査します。手がかりとしては、通帳、証券会社の取引報告書、自宅に届く郵便物、過去の確定申告書類などがあります。
預貯金の調査
口座がある可能性のある金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、JAバンクなど)に問い合わせ、口座の有無と残高を照会します。照会には、被相続人の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本など)や、相続人であることが確認できる書類が必要です。
多くの金融機関では、「残高証明書」と「過去の取引履歴」を取得できます。相続発生日時点の残高証明書は、相続税の計算や遺産分割協議で必要になります。
有価証券の調査
有価証券には、株式、投資信託、債券などがあります。証券会社(大手証券会社、ネット証券など)や、信託銀行(株式の特別口座など)に問い合わせ、取引口座の有無や保有銘柄、相続発生日時点の評価額を照会します。
証券会社からは、「残高証明書」や「取引報告書」を取得できます。株式については、上場株式であれば相続発生日の終値、投資信託であれば相続発生日の基準価額で評価するのが原則です。
ステップ2:金融機関・証券会社への連絡と一時停止
被相続人が亡くなったことを金融機関や証券会社に連絡すると、その口座は一時的に取引が停止されます。これは、不正な引き出しなどを防ぐための措置です。
口座が凍結されると、公共料金の引き落としやクレジットカードの支払いができなくなる可能性があります。生前に利用状況を確認しておくと良いでしょう。葬儀費用など、一定の範囲内で預貯金の一部を仮払いとして引き出すことができる制度もあります。
【注意!】
口座凍結されると、公共料金やカード引き落としができなくなることがあります。引き落とし口座の変更手続きは早めに行いましょう。
ステップ3:必要書類の準備・提出
金融機関や証券会社での手続きには、様々な書類が必要です。金融機関や証券会社によって必要書類が異なる場合があるため、事前にそれぞれの窓口やホームページで確認することが重要です。
一般的に必要となる書類は以下の通りです。
預貯金・有価証券の相続手続きに共通して必要な書類
- 被相続人の死亡診断書(または死亡届記載事項証明書)のコピー
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内などの期限がある場合が多い)
- 被相続人の通帳、キャッシュカード、証券会社の取引カードなど(紛失していても手続きは可能ですが、書類が増えることがあります)
遺言書がある場合に加えて必要な書類
- 遺言書原本
- 遺言書検認済証明書(自筆証書遺言の場合、法務局保管の場合は不要)
- 遺言執行者が指定されている場合はその方の選任審判書謄本など
遺産分割協議によって分割する場合に加えて必要な書類
- 遺産分割協議書
金融機関・証券会社所定の書類
- 相続に関する依頼書、解約・名義変更請求書など(金融機関や証券会社の窓口で取得するか、ホームページからダウンロードできます。相続人全員の署名・実印での押印が必要となることが多いです。)
その他、被相続人の住民票の除票や、相続人代表者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要になることもあります。事前に金融機関や証券会社に確認し、不足がないように準備しましょう。
ステップ4:名義変更または解約・払い戻し
必要書類が準備できたら、いよいよ金融機関や証券会社に提出し、名義変更や解約・払い戻しの手続きを行います。
預貯金の手続き
預貯金は、主に以下の2つの方法で手続きが可能です。
- 解約して払い戻す: 口座を解約し、残高を相続人の代表口座へ振り込んでもらう方法です。この場合、口座は閉じられます。
- 相続人へ名義変更する: 被相続人の口座を相続人の名義に変更する方法です。ただし、金融機関によっては名義変更を受け付けていない場合や、特定の条件がある場合があります。
どちらの方法を選択するかは、遺産分割協議の内容や相続人の意向によります。多くのケースでは、解約して代表相続人の口座にまとめて振り込む方法がとられます。
手続きにかかる期間は、金融機関や書類に不備がないかによって異なりますが、通常は書類提出から1週間〜数週間程度で完了することが多いです。
有価証券の手続き
有価証券も、預貯金と同様に名義変更または売却して換金するという選択肢があります。
- 相続人へ名義変更する(移管): 被相続人が保有していた有価証券を、相続人名義の証券口座へ移管する方法です。相続人自身が証券口座を持っていない場合は、事前に証券口座を開設する必要があります。
- 売却して換金する: 相続が発生した証券会社の口座で有価証券を売却し、その売却代金を相続人の代表口座へ振り込んでもらう方法です。売却益に対しては、原則として相続人が取得したときの価額(相続税評価額)を基に譲渡所得税が課税される可能性があります(みなし譲渡課税)。
どの方法を選択するかは、相続人の今後の資産運用方針や、銘柄、市場状況などを考慮して決定します。一般的には、遺産分割協議で分けにくい株式などを換金してから分割するケースも多く見られます。
手続きにかかる期間は、証券会社や手続き内容によって異なりますが、預貯金と同様に書類提出から一定の期間を要します。
ステップ5:(必要に応じて)相続税の申告・納付
相続財産の総額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。
遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
預貯金や有価証券も相続税の課税対象となる財産に含まれます。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続財産の評価、控除額の計算、申告書類の作成は非常に専門的な知識が必要となります。相続税の申告が必要となる場合は、税理士に相談することをおすすめします。
相続税の申告・納付は忘れずに!
相続税の申告と納付には厳格な期限があります。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかる可能性があります。
相続財産の評価や特例の適用など、専門的な判断が必要な場面も多いため、相続税が発生しそうな場合は早めに税理士に相談しましょう。税理士に依頼することで、適正な納税ができ、手続きの負担も軽減されます。
預貯金・有価証券の相続手続きでつまずきやすい点と注意点
預貯金や有価証券の相続手続きでは、いくつか注意しておきたい点があります。
必要書類の収集に時間がかかる
特に戸籍謄本等の収集は、被相続人の本籍地が複数回移っていたり、遠方の役場に請求したりする必要がある場合に時間がかかります。郵送で請求する場合は、往復の郵送期間も考慮する必要があります。
金融機関・証券会社ごとに手続きが異なる
同じ銀行でも支店によって対応が異なる場合や、ネット銀行とメガバンクで手続き方法や必要書類が異なる場合があります。事前に各金融機関・証券会社のホームページを確認したり、問い合わせたりして、必要な情報を把握することが重要です。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人同士で遺産の分け方について合意できない場合、遺産分割協議が長引くことがあります。遺産分割協議がまとまらないと、原則として預貯金や有価証券の名義変更・解約手続きを進めることができません。
遺産分割協議が難航する場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。遺産分割調停や審判といった裁判所の手続きを利用する方法もあります。
「みなし譲渡課税」に注意(有価証券)
相続した有価証券を売却した場合、相続人がその有価証券を取得したときの価額(原則として相続税評価額)と売却価額との差額に対して譲渡所得税が課税されます。これを「みなし譲渡課税」といいます。
相続税を納めている場合は、相続税額の一部を譲渡所得税から控除できる特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)があります。この特例を受けるためには、確定申告が必要です。詳しくは税理士に相談してください。
名義預金に注意
被相続人が家族名義で口座を開設し、そこに被相続人の資金を入金・管理していたような場合、その口座は名義は家族でも実質的には被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。これを「名義預金」といいます。
名義預金と判断されるかどうかは、資金の出所、管理状況、名義人が口座の存在を知っていたかなど、様々な要素を考慮して判断されます。税務調査で指摘されることが多い項目の一つですので、心当たりがある場合は税理士に相談することをおすすめします。
相続手続きを専門家に依頼するメリット
預貯金や有価証券を含む相続手続きは、時間と手間がかかる上に、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。このような場合、専門家に依頼することを検討するのも一つの方法です。
相続手続きを依頼できる主な専門家は以下の通りです。
- 弁護士: 相続人間でのトラブル(遺産分割協議がまとまらないなど)がある場合や、調停・審判が必要な場合に依頼できます。相続手続き全般を依頼することも可能です。
- 司法書士: 不動産の相続登記が専門ですが、預貯金や有価証券の相続手続きの一部を代行することも可能です(ただし、紛争性のある案件は弁護士の管轄となります)。
- 行政書士: 相続関係説明図や遺産分割協議書などの書類作成を依頼できます。金融機関での手続き代行も行う場合があります。
- 税理士: 相続税の計算、申告書類の作成、税務相談が専門です。相続税の申告が必要な場合は必ず相談すべき専門家です。
専門家に依頼することで、煩雑な手続きから解放され、精神的な負担を軽減することができます。また、法的に正確な手続きを行うことで、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
ただし、専門家に依頼すると費用が発生します。依頼する手続きの内容や、依頼する専門家によって費用は異なりますので、事前に見積もりを確認することが重要です。
専門家への依頼、費用の目安は?
専門家への依頼費用は、遺産の総額や手続きの複雑さ、依頼する専門家によって大きく異なります。
- 弁護士: 遺産分割協議の交渉や調停・審判を依頼する場合、遺産総額に応じた着手金や成功報酬が発生するのが一般的です。
- 司法書士・行政書士: 戸籍収集、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、金融機関手続き代行など、依頼する業務内容に応じて料金が設定されています。
- 税理士: 相続税申告を依頼する場合、遺産総額に応じた報酬体系が多いです。
まずは無料相談などを利用して、ご自身のケースでどのくらいの費用がかかるのかを確認してみましょう。
よくある質問(FAQ)
預貯金・有価証券の相続手続きに関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q: 口座が凍結されると、一切お金を引き出せなくなるの?
A: 原則として引き出しはできなくなりますが、「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、一定の範囲内で葬儀費用などのために預貯金の一部を引き出すことが可能です。詳しくは金融機関に問い合わせてください。
Q: 故人の口座がどこの銀行にあるか分からないのですが?
A: 自宅に届いた郵便物(キャッシュカードの更新案内、取引報告書など)、通帳、キャッシュカード、過去の確定申告書類などを探してみてください。手がかりがない場合は、心当たりのある金融機関に片っ端から問い合わせてみるしかありません。
Q: 相続手続きに期限はあるの?
A: 直接的な預貯金や有価証券の名義変更・解約に法律上の明確な期限はありません。しかし、相続税の申告・納付には10ヶ月以内という期限があります。また、遺産分割協議も長期間放置すると、新たな相続が発生して関係者が増え、手続きが複雑になる可能性があります。できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。
Q: 遺言書と遺産分割協議書の内容が違う場合は?
A: 原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。この場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する必要があります。
Q: 相続する株式に借入金の担保が設定されている場合は?
A: 担保権も一緒に引き継がれます。株式を相続する相続人は、その株式にかかる借入金についても責任を負うことになります。事前に金融機関に確認し、対応を検討する必要があります。
まとめ:計画的に、必要に応じて専門家も活用しよう
預貯金や有価証券の相続手続きは、一見複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つのステップを理解し、計画的に進めていけば、必ず完了できるものです。
まずは、相続人の確定と遺言書の有無の確認から始め、次に財産調査を行い、金融機関や証券会社と連携を取りながら手続きを進めていきましょう。
必要書類の収集や、遺産分割協議、相続税の申告など、専門的な知識が必要となる場面や、相続人間での話し合いが難しい場合は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士といった専門家の力を借りることも有効です。</専門家に相談することで、手続きの負担が軽減されるだけでなく、法的に正確な手続きを行うことができ、後々のトラブルを防ぐことにも繋がります。
相続は、故人が遺してくれた大切な財産と想いを、次の世代へ繋いでいく機会です。この記事が、その手続きをスムーズに進めるための一助となり、皆様が安心して相続を終えられることを願っています。
不明な点や不安なことがあれば、一人で抱え込まず、信頼できる専門家や公的機関に相談することをおすすめします。
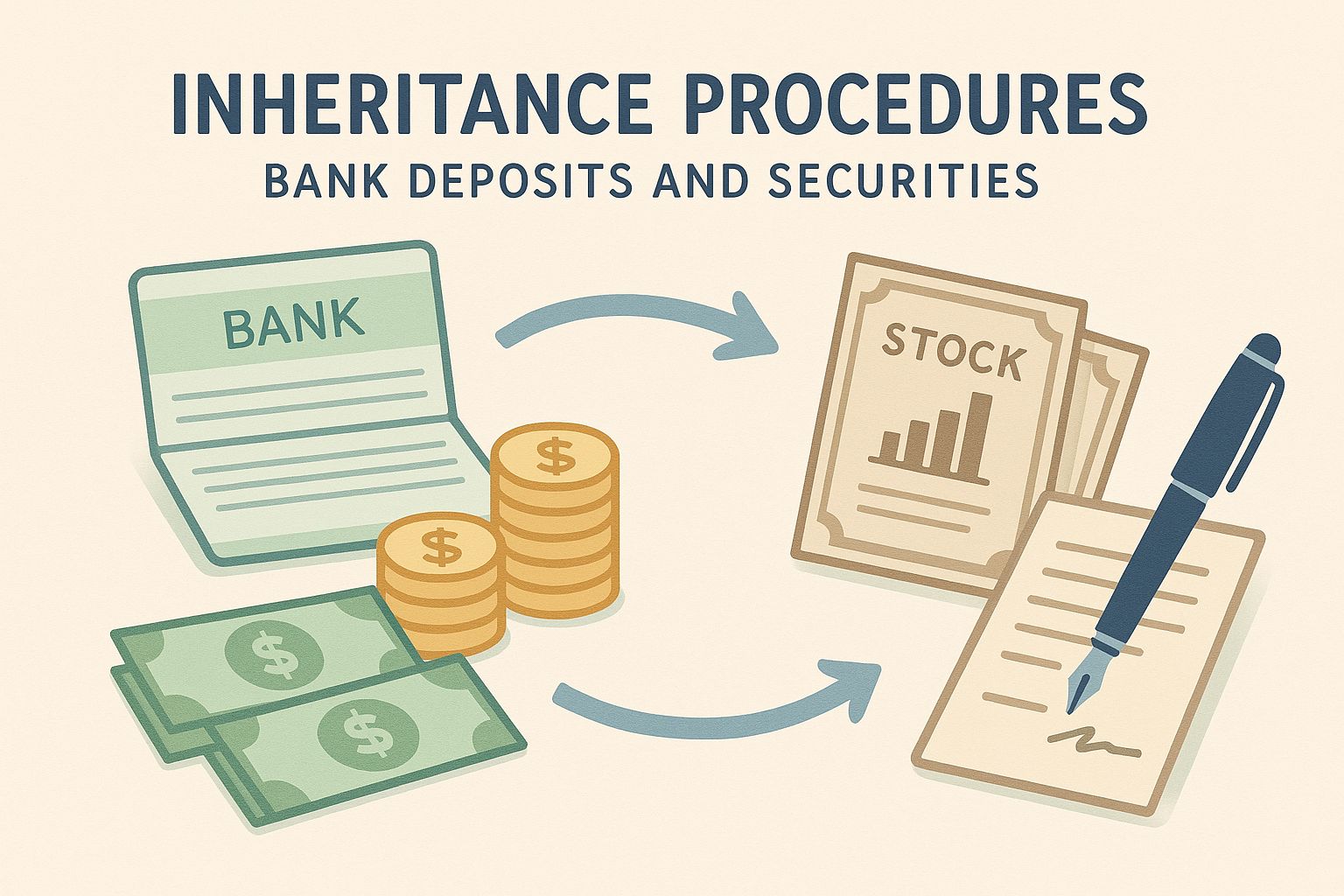


コメント