大切なご家族が亡くなられた後、残された資産の相続手続きは、ただでさえ大変なものです。
もし、その資産の中に「海外にある資産」が含まれているとしたら、どうでしょうか?
「どこから手をつけていいか分からない…」
「日本の手続きとは全然違うの?」
「税金はどうなるの?」
様々な不安が頭をよぎるかもしれません。
国内の資産相続とは異なり、海外資産の相続手続きは、関係する国が複数になることで、法律、税制、言語、手続きの煩雑さなど、一気にハードルが高くなります。
しかし、安心してください。
海外資産の相続は確かに複雑ですが、そのポイントと適切な手順、そして専門家のサポートを得ることで、混乱を最小限に抑え、スムーズに進めることが可能です。
この記事では、海外資産がある場合の相続手続きについて、なぜ複雑なのか、生前にできる準備、相続発生後の具体的な流れ、そして知っておくべき国の制度や専門家の活用方法まで、徹底的に解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、海外資産相続に関する不安が解消され、取るべき行動が明確になるはずです。ぜひ、じっくりとお読みください。
なぜ海外資産の相続は「難しい」と言われるのか?国内相続との違い
まず、なぜ海外資産の相続が国内資産の相続と比べて格段に難しいのか、その理由を明確にしておきましょう。主な要因は以下の通りです。
1.適用される法律が複雑
相続は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地や国籍、または財産の所在地など、様々な要素によって「どこの国の法律が適用されるか」が決まります。
もし日本に住んでいた方が海外に資産を残して亡くなった場合、日本の民法が適用される部分と、海外の法律が適用される部分が出てくる可能性があります。
例えば、不動産の相続については、その不動産がある国の法律が適用されることが多いです。これは「所在地法主義」と呼ばれる考え方です。
また、動産(預貯金や有価証券など)については、被相続人の最後の住所地の法律や国籍の法律が適用されるなど、国によって判断が異なります。
このように、複数の国の法律が絡み合い、どの法律に基づいて手続きを進めるべきかを判断すること自体が最初の難関となります。
2.税金の問題(二重課税の可能性)
相続においては、相続税が大きな関心事です。海外資産がある場合、日本の相続税だけでなく、その資産がある国の相続に関する税金も課される可能性があります。
例えば、アメリカに不動産がある場合、日本の相続税の課税対象になるだけでなく、アメリカでも相続税(Estate Tax)や贈与税(Gift Tax)のような税金が課される可能性があります。
このように、同じ財産に対して複数の国から税金が課されることを「国際的な二重課税」と呼びます。これは相続人にとって大きな負担となります。
もちろん、多くの国との間には租税条約や、国内法上の「外国税額控除」といった二重課税を排除・軽減するための仕組みがありますが、その適用関係や計算方法を理解し、適切に申告するのは非常に専門的な知識が必要です。
3.手続きの煩雑さと時間
海外の金融機関や役所とのやり取りは、言語の壁はもちろんのこと、手続きの進め方、必要書類、文化や慣習の違いなどにより、非常に時間と労力がかかります。
必要書類一つとっても、日本の印鑑証明書や住民票のような書類が海外では存在しない場合や、特定の書式や公証が必要となる場合があります。これらの書類の収集、翻訳、公証といった作業も手間がかかります。
また、物理的な距離があるため、現地に出向く必要がある場合や、郵送のやり取りに時間がかかることも、手続きを遅らせる要因となります。
4.財産の全体像の把握が困難
国内の資産であれば、通帳や権利証、登記簿などを確認することで比較的容易に全体像を把握できます。
しかし、海外にどのような資産がどれだけあるのか、被相続人が生前にリスト化していない限り、相続人が全てを把握するのは非常に難しい場合があります。
見慣れない国の金融機関からの郵便物や、聞いたことのない会社の株式などが出てきて、それが資産なのかどうかの判断に困るケースも少なくありません。
相続発生までにできること:生前対策の重要性
海外資産がある場合の相続をスムーズに進めるためには、被相続人が生前に適切な準備をしておくことが何よりも重要です。
「終活」の一環として、これらの対策を講じることで、残された家族の負担を大きく軽減できます。
1.海外資産を含む全ての財産のリストアップと所在の明確化
まずは、国内外にどのような資産がどれだけあるのかを正確に把握することが出発点です。
- 預貯金: 銀行名、支店名、口座番号、口座名義、残高(おおよそでも良い)、インターネットバンキングのID・パスワードなど
- 有価証券: 証券会社名、口座番号、保有銘柄、株数、インターネット取引のID・パスワードなど
- 不動産: 所在地の国、都市、正確な住所、種類(土地、建物、マンションなど)、登記情報、評価額など
- その他資産: 生命保険、貴金属、美術品、骨董品、デジタル資産(仮想通貨など)など
これらの情報をリスト化し、関連書類(通帳、証券、権利証、契約書など)の保管場所を明確にしておきましょう。
可能であれば、海外の金融機関や不動産業者、管理会社などの連絡先も控えておくと、相続発生後の問い合わせがスムーズになります。
2.遺言書の作成(国内外の有効性を考慮)
遺言書は、相続財産を誰にどのように引き継がせるかを明確に意思表示できる強力な手段です。
海外資産がある場合、遺言書は特に重要になります。
日本の法律に則った遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)を作成するのはもちろんですが、海外の法律に則った遺言書を作成することも検討が必要です。
例えば、不動産がある国の法律で有効な遺言書を作成しておくと、その国での名義変更手続きがスムーズに進む可能性があります。
ただし、複数の遺言書を作成する場合、内容に矛盾がないように細心の注意が必要です。日本の専門家と海外の専門家が連携して作成することをお勧めします。
また、「国際遺言」と呼ばれる、複数の国で有効となりうる形式の遺言書も存在しますが、対応している国が限られているため、専門家によく相談することが重要です。
3.相続人の確認と情報共有
誰が相続人になるのかを明確にし、相続人が海外資産の存在を把握しているか確認しておきましょう。
海外資産に関する情報や、それをリスト化した書類の保管場所などを、信頼できる家族に伝えておくことも重要です。
相続発生後に初めて海外資産の存在を知った場合、その調査だけでも時間を要し、手続きが遅れる原因となります。
4.専門家への早期相談
海外資産の相続は専門性が非常に高いため、生前の早い段階から国際相続に詳しい弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続対策の方向性、遺言書の内容、税金に関するアドバイスなど、専門家から具体的な助言を得ることで、より効果的な準備が可能となります。
5.海外の法律や税制に関する情報収集
資産がある国の相続に関する基本的な法律や税制について、可能な範囲で情報収集をしておくことも有効です。
ただし、素人判断は禁物ですので、あくまで概要を把握する程度にとどめ、詳細は専門家に確認するようにしましょう。
相続発生後の具体的な手続きとポイント
残念ながら、生前対策が十分でなかった場合でも、相続発生後に適切な手続きを進めることは可能です。
ここでは、相続発生後の具体的な流れと、それぞれの段階でのポイントを解説します。
1.相続人の確定
まずは、誰が法定相続人になるのかを確定させます。戸籍謄本などを収集して確認します。
海外に住んでいる相続人がいる場合、その国の公的な書類が必要になることもあります。
2.相続財産の調査と評価
国内外の全ての相続財産を調査し、リストアップします。生前対策でリストがあればこれを活用します。
海外資産については、現地の金融機関や登記所などへの問い合わせが必要になる場合があります。
財産の評価も重要です。特に海外不動産などは、現地の評価方法や通貨での評価を円に換算する必要があります。為替レートの適用時期にも注意が必要です。
海外の専門家(不動産鑑定士など)に評価を依頼する必要がある場合もあります。
3.相続方法の選択
相続財産の全体像が把握できたら、相続人全員で「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれを選択するかを決めます。
海外資産に借金(負債)が含まれている場合など、限定承認や相続放棄を検討することもあります。相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に行う必要があるため、迅速な判断が必要です。
海外資産に紐づく負債についても、正確な情報を把握する必要があります。
4.相続税の申告・納付(日本)
日本の相続税の申告は、原則として相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
海外資産も日本の相続税の課税対象となりますので、全ての財産を合算して相続税額を計算します。
ここで重要になるのが「外国税額控除」です。海外で相続に関連する税金を納めた場合、一定の要件を満たせば、日本の相続税額からその海外で納めた税金の一部または全部を差し引くことができます。
外国税額控除の計算は複雑であり、適用できる税金の種類や金額には上限があるため、国際税務に詳しい税理士に必ず相談してください。
必要書類として、海外資産の評価証明書や、海外で相続に関連して税金を納めたことを証明する書類などが必要になります。これらの書類の収集、翻訳、公証にも時間がかかります。
5.海外での相続手続きと納税
資産がある国の法律に基づいた相続手続きが必要です。
国の制度によっては、裁判所の手続き(例:アメリカのProbate、イギリスのGrant of Representationなど)が必要になる場合があります。
また、その国で相続に関する税金が課される場合は、その国の税法に基づいて申告・納付を行います。税金の計算方法や申告期限は国によって大きく異なります。
これらの手続きは、現地の弁護士や税理士などの専門家を通じて行うのが一般的です。
6.海外資産の名義変更・換価
海外の不動産や預貯金、有価証券などの名義を相続人に変更したり、売却して現金化したりする手続きを行います。
これも、資産がある国の金融機関や登記所などの規定に従って進める必要があります。
必要書類は国や金融機関によって異なりますが、日本の相続を証明する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)の英訳・公証済みのものや、現地の法律家が作成した書類などが求められることが多いです。
特に海外の金融機関は本人確認や資金移動に関する規制が厳しいため、手続きに時間がかかる傾向があります。
7.必要書類の準備と翻訳・公証
国内外の相続手続きには、様々な公的書類が必要です。
日本の書類を海外の機関に提出する場合、英語など現地の言語への翻訳が必要です。単に翻訳するだけでなく、公証役場や外務省によるアポスティーユ認証(または領事認証)が必要となる場合が多いです。
これらの手続きも時間と手間がかかりますので、早めに準備を始めることが重要です。
知っておきたい!いくつかの国の相続制度概観
海外の相続制度は国によって千差万別です。ここでは、代表的な国の相続制度の概略に触れてみましょう。
※これらはあくまで一般的な情報であり、個別のケースや最新の情報については専門家にご確認ください。
アメリカ合衆国
- 州によって相続に関する法制度が異なります。
- 遺言書がない場合や遺言書の執行には、裁判所が関与する「Probate(プロベート)」という手続きが必要になることが一般的です。プロベートは時間と費用がかかる傾向があります。
- 連邦レベルでの相続税(Estate Tax)や贈与税(Gift Tax)があり、一定額以上の資産に課税されます。州によっては独自の相続税や遺産税を課す場合もあります。
イギリス
- 相続手続きは「Probate」または「Letters of Administration」と呼ばれる、裁判所からの執行許可を得る手続きが中心となります。
- 「Inheritance Tax(相続税)」が課されますが、配偶者への相続や特定の財産については非課税枠や軽減措置があります。
フランス
- 遺留分(相続人に最低限保証される相続分)に関する規定があります。
- 相続税(Droits de succession)は、相続人との関係性によって税率が異なります。
ドイツ
- 遺留分に関する規定があります。
- 相続税(Erbschaftsteuer)は、相続人との関係性によって税率や控除額が異なります。
中国
- 相続に関する法律や税制は変化する可能性があります。
- 不動産などの相続には、現地の公証役場での手続きが必要になることが多いです。
このように、国によって適用される法律や手続き、税金の種類や税率が全く異なります。ご自身が資産を持つ国の制度について、正確な情報を把握することが不可欠です。
海外資産相続で絶対に外せない「専門家」の活用
これまで見てきたように、海外資産の相続は非常に複雑で専門的な知識が不可欠です。
適切な専門家のサポートを得ることは、手続きをスムーズに進め、予期せぬトラブルや追加の税負担を避けるために最も重要なポイントと言えます。
どのような専門家に相談すべきか?
- 日本の弁護士: 国際相続案件の経験豊富な弁護士は、複数の国の法律が絡む場合の法的判断や、相続人間の調整、トラブル発生時の対応など、幅広いサポートが可能です。
- 日本の税理士: 国際税務に詳しい税理士は、日本の相続税申告における海外資産の評価、外国税額控除の計算、海外での納税との調整など、税金に関する専門的なアドバイスや手続きを代行してくれます。
- 日本の司法書士: 不動産の相続登記など、国内の手続きをサポートしてくれます。海外不動産に関する登記手続きについては、現地の司法書士や弁護士との連携が必要になります。
- 海外の専門家(弁護士、税理士、会計士など): 資産がある国の法律や税制、手続きに精通した現地の専門家は必須です。日本の専門家と連携して、現地での手続きを代行してもらいます。
専門家選びのポイント
- 国際相続の経験: 海外資産を含む相続案件の取り扱い経験が豊富であるかを確認しましょう。
- 連携体制: 必要に応じて、日本の専門家と海外の専門家がスムーズに連携できる体制を持っているかどうかも重要なポイントです。
- 説明の分かりやすさ: 複雑な内容を、専門用語を使わずに分かりやすく説明してくれるかどうかも、信頼できる専門家を見つける上で大切です。
- 費用: 事前に費用体系を確認し、納得した上で依頼するようにしましょう。
複数の専門家から話を聞き、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことをお勧めします。多くの場合、最初の相談は無料で行っている専門家もいます。
よくある質問(Q&A)
海外資産相続に関して、よくある質問とその回答をご紹介します。
Q1. 海外に「隠し資産」があった場合、どうなりますか?
A1. 海外に申告していない資産が後から見つかった場合、日本の相続税の申告漏れとなり、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。また、資産がある国での税法に違反している可能性も否定できません。故人の名誉のためにも、相続人全員で協力して全ての資産を正確に把握し、適切に申告することが非常に重要です。
Q2. 相続税の二重課税は必ず避けられますか?
A2. 日本と多くの国との間には二重課税を排除・軽減するための仕組み(租税条約や外国税額控除)がありますが、必ずしも全ての二重課税が完全に解消されるわけではありません。また、その適用には複雑な計算や手続きが必要です。国際税務に詳しい税理士に必ず相談し、適切な申告を行うことで、可能な限りの軽減措置を受けることができます。
Q3. 海外資産の相続手続きにはどれくらいの時間がかかりますか?
A3. 海外資産の種類、所在国、手続きの複雑さ、関係者の協力状況などによって大きく異なりますが、国内の相続手続きに比べて時間がかかるのが一般的です。数ヶ月で完了する場合もあれば、数年を要するケースも少なくありません。特に裁判所の手続きが必要な場合や、関係国が複数にわたる場合は、長期化する傾向があります。生前対策をしっかり行い、相続発生後は早めに専門家に相談することが、期間短縮につながります。
Q4. 海外の不動産を相続しましたが、売却したいと考えています。手続きは日本からでもできますか?
A4. 原則として、不動産がある国の法律や手続きに従って売却手続きを進める必要があります。多くの場合、現地の不動産業者や弁護士に依頼して手続きを代行してもらうことになります。日本から指示を出すことは可能ですが、必要書類の準備や送付、国際送金など、手間がかかることが多いです。現地の専門家と密に連携することが成功の鍵となります。
まとめ:海外資産の相続も、適切な準備と専門家で乗り越えられる
海外資産がある場合の相続手続きは、国内の相続に比べて確かに複雑で、多くのハードルがあります。
しかし、必要以上に恐れることはありません。
重要なのは、
- 生前の準備を怠らないこと(財産の把握、遺言書の検討など)
- 相続発生後は、できるだけ早く全ての資産を正確に把握すること
- 国際相続や国際税務に詳しい専門家のサポートを必ず得ること
- 関係者と密にコミュニケーションを取り、協力して手続きを進めること
これらのポイントを押さえ、一つずつ丁寧に進めていけば、海外資産の相続も適切に完了させることができます。
この記事が、海外資産の相続に直面されている方々にとって、一筋の光となり、不安を解消し、取るべき行動を明確にする一助となれば幸いです。
もし、ご自身のケースでは具体的にどうすれば良いのか、どのような専門家に相談すべきかなど、さらに詳細な情報や個別の状況に合わせたアドバイスが必要な場合は、国際相続を取り扱っている専門家にご相談されることを強くお勧めします。
相続は、故人が残された大切な財産と想いを次世代へ引き継ぐための重要なプロセスです。適切な手続きを行い、円満な形で完了させましょう。


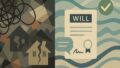
コメント