「終活」や「相続」という言葉に触れる機会が増えたけれど、「結局、誰が相続人になるんだろう?」と疑問に思っていませんか?
家族構成は人それぞれ。配偶者はいる?子どもは?両親は?兄弟姉妹はいるけれど、疎遠になっている…など、様々な状況があるかと思います。
相続は、大切なご家族が遺された財産を引き継ぐための、非常に重要な手続きです。そして、その手続きを進める上で、まず最初に、そして最も重要になるのが「誰が相続人になるのか」を正確に把握することなのです。
この記事では、民法で定められている「法定相続人」の範囲と順位について、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。
ご自身の、またはご家族の状況に照らし合わせながら読み進めていただくことで、「うちの場合は〇〇さんが相続人になるんだな」ということが明確になり、相続に向けた第一歩を踏み出すことができるはずです。
この記事を読めば、以下のことが分かります。
- なぜ法定相続人を知る必要があるのか
- 法定相続人とは具体的に誰のことか
- 法定相続人にはどのような順位があるのか
- あなたの家族構成では誰が法定相続人になるのか(具体的なケースで解説)
- もしもの時に備えて、今からできることは何か
難しそう…と感じる必要はありません。相続に関する疑問や不安を解消し、安心して将来を迎えるための知識を、一緒に確認していきましょう。
なぜ「法定相続人」を知ることが最初の一歩なのか?
相続が発生したとき、遺された財産(プラスの財産:預貯金、不動産、株式など、マイナスの財産:借金など)は、民法の規定に基づき、亡くなった方の相続人が引き継ぐことになります。
この「相続人」が誰なのかが分からなければ、相続手続きは一切先に進めることができません。
例えば…
- 故人の銀行口座から預金を引き出す
- 故人の不動産の名義変更をする
- 相続税の申告をする
- 遺産分割協議をする
これらの手続きを行うためには、故人の戸籍謄本などを取得し、誰が相続人であるかを確定させる必要があるのです。
もし、相続人の範囲を間違えて認識していた場合、後になって「あの人も相続人だったのに!」と判明し、遺産分割協議が無効になったり、相続トラブルに発展したりする可能性もゼロではありません。
だからこそ、相続について考える上で、まず最初に「法定相続人」を正しく理解することが、何よりも大切なのです。
「法定相続人」とは?民法で定められた相続できる人
「法定相続人」とは、その名の通り、民法によって「被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利があると定められている人」のことです。
遺言書がない場合、相続人はこの法定相続人の範囲で決まります。また、遺言書がある場合でも、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取り分)に関わるため、法定相続人を把握しておくことは非常に重要です。
法定相続人には、常に相続人となる人と、順位によって相続人になる人がいます。
常に相続人となる人:配偶者
被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、その配偶者は**常に相続人**となります。
これは、配偶者がどのような家族構成であっても変わりません。例えば、被相続人に子どもがいても、親がいても、兄弟姉妹がいても、配偶者は必ず相続人になります。
ただし、ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある人のみを指します。いわゆる内縁の妻や夫は、残念ながら法定相続人にはなれません。
順位によって相続人となる人
配偶者以外の法定相続人には、以下のように相続できる順位が定められています。
第一順位:子
被相続人の子どもは、第一順位の法定相続人です。
子どもがいる場合、配偶者と一緒に相続人になります。子どもの人数が複数いる場合は、子ども全員が同じ順位で相続人となります。
子の代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
もし、被相続人が亡くなるよりも前に、その子どもが既に亡くなっていた場合、その亡くなった子どもの子ども(被相続人から見て孫)が、亡くなった子どもに代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
さらに、もし孫も亡くなっている場合は、その孫の子ども(被相続人から見てひ孫)が代襲相続します。子の代襲相続は、下の世代に限りなく続いていきます。
養子も、法律上の親子関係があるため、実子と同じように法定相続人となります。
第二順位:直系尊属(ちょっけいそんぞく)
被相続人に子どもやその代襲相続人がいない場合、第二順位の法定相続人である「直系尊属」が相続人となります。
直系尊属とは、被相続人よりも上の世代の親族、つまり「父母」や「祖父母」のことです。
父母がいる場合は父母が相続人となり、父母が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。この場合も、世代的に近い親等の人が優先されます。例えば、父母のうちどちらか一方でも存命であれば、祖父母は相続人にはなれません。
直系尊属が相続人になる場合、配偶者がいれば配偶者と共に相続人になります。
第三順位:兄弟姉妹
被相続人に子どもやその代襲相続人も、直系尊属もいない場合、第三順位の法定相続人である「兄弟姉妹」が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人になる場合も、配偶者がいれば配偶者と共に相続人になります。
兄弟姉妹の代襲相続とは?
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その亡くなった兄弟姉妹の子ども(被相続人から見て甥姪)が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、子の代襲相続と異なり、甥姪まで一代限りです。甥姪が亡くなっていたとしても、その子ども(被相続人から見ていとこ)が代襲相続することはありません。
異母兄弟・異父兄弟の扱い
父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)も、法律上の兄弟姉妹として法定相続人となります。ただし、後述する法定相続分において、父母両方を同じくする兄弟姉妹とは異なる割合になります。
フローチャートで確認!あなたの家族の法定相続人は?
少し複雑に感じたかもしれませんが、簡単にまとめると、法定相続人は以下の順序で決まります。
まず、**配偶者がいれば、常に配偶者は相続人**です。
その上で、以下の順位で確認します。
- 被相続人に子どもやその代襲相続人はいますか?
- いる場合: 配偶者と一緒に、子どもやその代襲相続人が相続人です。他の親族は相続人になりません。
- いない場合: 次の順位に進みます。
- 被相続人に父母や祖父母などの直系尊属はいますか?
- いる場合: 配偶者と一緒に、父母や祖父母などの直系尊属が相続人です。兄弟姉妹やその代襲相続人は相続人になりません。
- いない場合: 次の順位に進みます。
- 被相続人に兄弟姉妹やその代襲相続人はいますか?
- いる場合: 配偶者と一緒に、兄弟姉妹やその代襲相続人が相続人です。
- いない場合: 配偶者のみが相続人となります。(配偶者もいない場合は、法定相続人がいないことになります。)
この流れを頭に入れておくと、ご自身の家族構成で誰が法定相続人になるかが分かりやすくなります。
具体例で見てみよう!こんな家族の場合、誰が相続人?
いくつかの家族構成を例に、具体的に誰が法定相続人になるかを見ていきましょう。
例1:夫が亡くなったケース(妻、子ども2人)
夫が被相続人、妻と子ども2人がいます。
この場合、配偶者である妻は常に相続人です。子どもは第一順位の法定相続人です。
したがって、法定相続人は**妻と子ども2人**になります。
例2:夫が亡くなったケース(妻のみ、子どもなし、両親健在)
夫が被相続人、妻がいます。子どもはいません。夫の両親は健在です。
妻は常に相続人です。子どもがいないため、第二順位の直系尊属を確認します。夫の両親が健在であるため、夫の両親が直系尊属として相続人になります。
したがって、法定相続人は**妻と夫の両親**になります。
例3:夫が亡くなったケース(妻のみ、子どもなし、両親・祖父母他界、兄1人)
夫が被相続人、妻がいます。子どもはいません。夫の両親、祖父母は既に亡くなっています。夫には兄が1人います。
妻は常に相続人です。子ども、直系尊属がいないため、第三順位の兄弟姉妹を確認します。夫には兄がいるため、兄が兄弟姉妹として相続人になります。
したがって、法定相続人は**妻と夫の兄**になります。
例4:夫が亡くなったケース(妻のみ、子どもなし、両親・祖父母他界、兄は既に他界、その兄に子ども(甥)1人)
夫が被相続人、妻がいます。子どもはいません。夫の両親、祖父母は既に亡くなっています。夫には兄がいましたが、夫よりも先に亡くなっています。その亡くなった兄には子ども(夫から見て甥)が1人います。
妻は常に相続人です。子ども、直系尊属がいないため、第三順位の兄弟姉妹を確認します。夫の兄は既に亡くなっていますが、兄には子ども(甥)がいるため、甥が代襲相続人として相続人になります。
したがって、法定相続人は**妻と夫の甥**になります。
例5:夫が亡くなったケース(妻なし、子ども2人)
夫が被相続人、妻は既に亡くなっています。子どもが2人います。
妻がいないため、第一順位の子どもを確認します。夫には子どもが2人いるため、子ども2人が相続人になります。
したがって、法定相続人は**子ども2人**になります。
例6:夫が亡くなったケース(妻なし、子どもなし、両親健在)
夫が被相続人、妻は既に亡くなっています。子どもはいません。夫の両親は健在です。
妻がいないため、第一順位の子どもを確認しますが、いません。第二順位の直系尊属を確認します。夫の両親が健在であるため、両親が相続人になります。
したがって、法定相続人は**夫の両親**になります。
例7:夫が亡くなったケース(妻なし、子どもなし、両親・祖父母他界、兄1人、妹1人)
夫が被相続人、妻は既に亡くなっています。子どもはいません。夫の両親、祖父母は既に亡くなっています。夫には兄が1人、妹が1人います。
妻がいないため、第一順位の子ども、第二順位の直系尊属を確認しますが、いずれもいません。第三順位の兄弟姉妹を確認します。夫には兄と妹がいるため、兄と妹が相続人になります。
したがって、法定相続人は**夫の兄と妹**になります。
このように、家族構成によって法定相続人は変わってきます。ご自身の、またはご家族の状況に当てはめて考えてみてください。
相続人の範囲から外れるケース:相続欠格と相続廃除
法定相続人であっても、例外的に相続権を失うケースがあります。それが「相続欠格」と「相続廃除」です。
相続欠格(そうぞくけっかく)
これは、民法で定められた一定の事由に該当する場合、相続人が当然に相続権を失う制度です。例えば、被相続人を故意に死亡させたり、詐欺や脅迫によって遺言書を偽造・変造させたりした場合など、相続に関する重大な不正行為を行った場合に適用されます。
相続欠格に該当すると、裁判所の手続きなどを経ることなく、法律上当然に相続権を失います。また、代襲相続も認められません。
相続廃除(そうぞくはいじょ)
これは、被相続人に対して、虐待をしたり重大な侮辱を加えたり、その他著しい非行があった相続人の相続権を、被相続人の意思によって奪う制度です。遺言によって行うか、生前に家庭裁判所に申し立てて行います。
相続廃除が認められるには、単なる不仲といった理由では難しく、法律が定める一定の要件を満たす必要があります。相続廃除が認められた場合、その相続人は相続権を失いますが、代襲相続は認められます。
これらのケースは稀ではありますが、法定相続人を考える上で、例外として知っておくと良いでしょう。
あなたの家族の法定相続人を確認するには?
ご自身の家族の法定相続人を正確に確認するためには、被相続人となる方の**出生から死亡までの連続した戸籍謄本**を取得することが必要です。
戸籍謄本をたどることで、いつ、誰と婚姻し、いつ、誰が生まれ、養子縁組はあったか、離婚はあったか、いつ亡くなったかなど、家族関係の全ての記録を確認することができます。
特に、代襲相続が発生している可能性がある場合や、再婚をしている場合、認知した子どもがいる場合など、家族関係が複雑な場合には、戸籍謄本の収集と確認が非常に重要になります。
ご自身で戸籍謄本を集めることも可能ですが、役所への請求や、複雑な戸籍を読み解く作業は時間と手間がかかることも少なくありません。必要に応じて、行政書士や司法書士といった専門家に依頼することも検討しましょう。
もしもの時に備えて、今からできること
法定相続人の範囲を理解し、ご自身の家族の状況を確認することは、将来の相続に備えるための重要なステップです。
相続は「争族」とも言われるように、遺されたご家族の間でトラブルになることも少なくありません。こうしたトラブルの多くは、準備不足や、相続に関する知識の不足から起こることが多いと言われています。
法定相続人を知るだけでなく、さらに踏み込んで、以下のようなことを考えてみることをお勧めします。
- 相続財産を把握する: どのような財産(預貯金、不動産、株式、借金など)がどれくらいあるのかをリストアップしてみましょう。
- 遺言書を作成する: 誰にどの財産を相続させたいか、具体的な意思がある場合は、遺言書を作成することで、ご自身の希望を実現し、残された家族の負担を減らすことができます。
- 家族と話し合う: 相続について、デリケートな話題かもしれませんが、ご家族と話し合う機会を持つことも大切です。お互いの気持ちや考えを共有することで、誤解やトラブルを防ぐことに繋がります。
- 専門家に相談する: 相続財産が多い、家族構成が複雑、相続人の間で不安があるなど、少しでも心配なことがある場合は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に相談してみましょう。早い段階で専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続に繋がります。
「まだ早いかな…」と思うかもしれませんが、終活や相続の準備に「早すぎる」ということはありません。元気なうちに、冷静に、しっかりと準備をしておくことが、ご自身のため、そして大切なご家族のために、きっと役立つはずです。
まとめ:法定相続人の確認は、安心できる将来への第一歩
この記事では、相続の基本中の基本である「法定相続人の範囲と順位」について詳しく解説しました。
法定相続人は民法によって定められており、配偶者(常に相続人となる)と、一定の順位で相続人となる親族(子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹や甥姪など)が含まれます。
ご自身の家族では誰が法定相続人になるか、イメージが掴めたでしょうか?
法定相続人を正しく理解することは、相続手続きを円滑に進めるためだけでなく、将来の相続について考え、ご家族と話し合い、必要に応じて遺言書を作成するなど、様々な準備の出発点となります。
相続について何も分からない、何から始めれば良いか分からない、と感じていた方も、この記事を読んで、少しでも不安が解消され、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
もし、この記事を読んでもまだ疑問が残る場合や、個別の状況について詳しく知りたい場合は、遠慮なく相続の専門家にご相談ください。
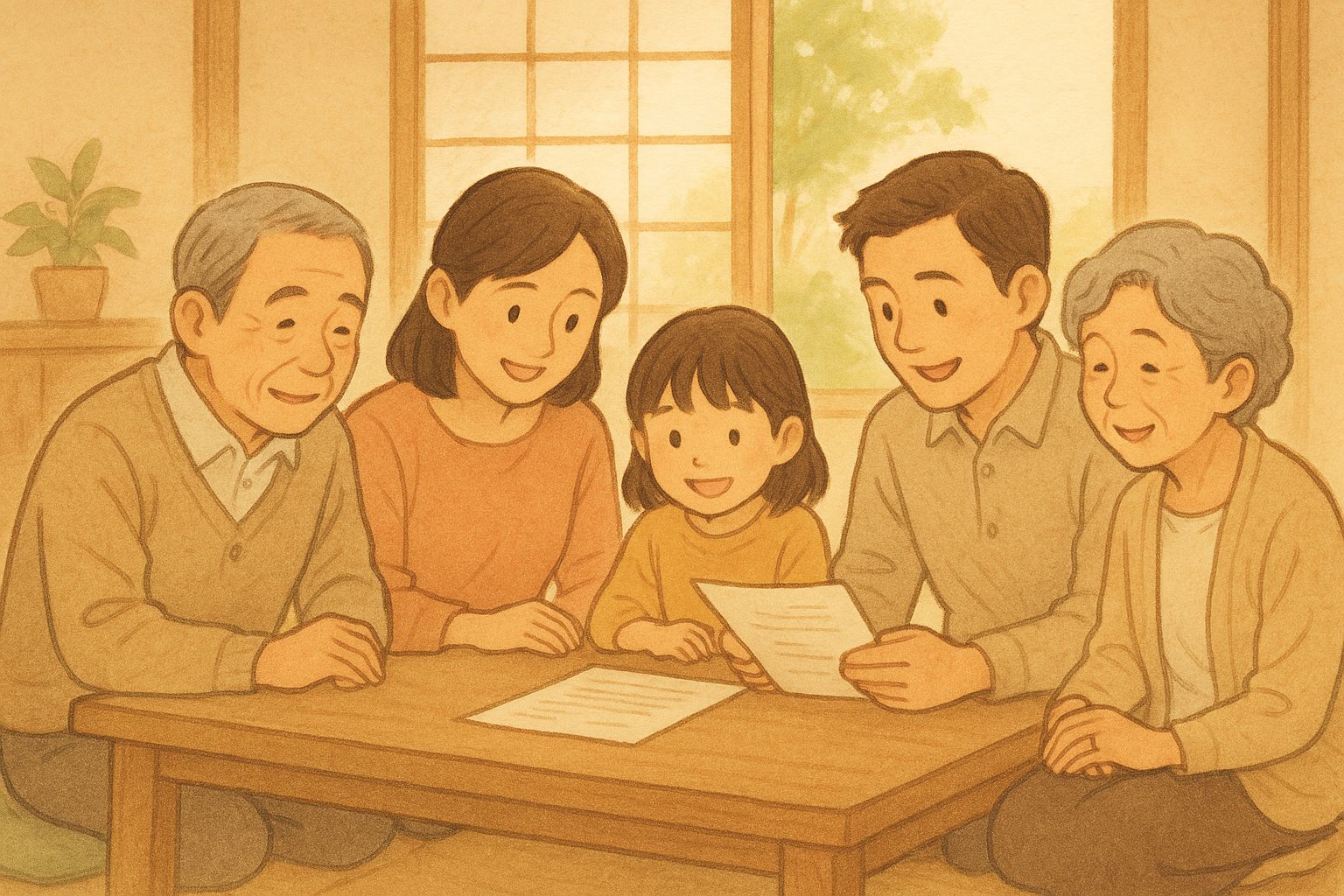


コメント