大切なご家族が亡くなられた後、悲しみに暮れる間もなく直面するのが様々な手続きです。その中でも、「相続登記」は多くの方が「難しそう」「面倒くさそう」と感じる手続きの一つではないでしょうか。
不動産の所有者が亡くなった場合、その名義を相続人に変更するための手続きが相続登記です。これまでは法務局に出向いて、たくさんの書類を提出し、申請書を作成する必要がありました。
「仕事で平日昼間は法務局に行けない…」「遠方の不動産だから移動が大変…」「書類の書き方がわからない…」
そういった悩みから、つい手続きを後回しにしてしまい、気づいたら長い年月が経過していた…というケースも少なくありません。
しかし、時代は進化しています!実は、この相続登記、オンラインで申請できるようになったことをご存知ですか?
「オンラインって、どういうこと?」「本当に自宅で完結できるの?」「自分でもできるの?」
この記事では、そんな疑問をお持ちのあなたに向けて、相続登記のオンライン申請について、そのメリット・デメリット、手続きの流れ、必要な準備、そして「自分でやる」と「専門家に依頼する」の違いまで、徹底的に分かりやすく解説します。
この記事を読めば、相続登記のオンライン申請があなたにとって有効な選択肢なのかどうか、判断できるようになるはずです。ぜひ最後までお読みください。
相続登記とは?なぜ必要なの?
まず、相続登記とは何か、そしてなぜ必要なのかを簡単におさらいしましょう。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続人へ変更する登記手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」といいます。
この手続きを行わないと、登記簿上の所有者は亡くなった方の名義のままになってしまいます。
では、相続登記をしないとどうなるのでしょうか?
- 不動産の売却や賃貸ができない: 不動産を売ったり貸したりするには、所有者名義が現在の所有者(相続人)になっている必要があります。
- 新たな担保設定ができない: 不動産を担保にお金を借りることもできません。
- さらに相続が発生した場合に複雑化する: 相続登記をしないまま次の相続が発生すると、権利関係が複雑になり、手続きが非常に煩雑になります。いわゆる「数次相続」です。
- 相続人の間でトラブルになる可能性がある: 名義が変更されていないことで、誰が真の所有者なのか不明確になり、相続人同士や、その先の世代でトラブルに発展するリスクが高まります。
- 法改正により義務化される可能性: 現在、相続登記は義務ではありませんが、法改正により将来的に義務化される方向で議論が進んでいます。※【追記】2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました!正当な理由なく義務を怠ると過料が科される可能性があります。詳細は法務省の情報を確認してください。
このように、相続登記は不動産を所有する上で非常に重要な手続きなのです。そして、この手続きをよりスムーズに行うための選択肢として、「オンライン申請」が登場しました。
これまでの「紙」による申請と何が違う?
オンライン申請を理解するために、これまでの「紙」による申請がどのようなものだったか、そしてオンライン申請との違いを見ていきましょう。
これまでの紙による申請
これまでは、以下の手順で手続きを行うのが一般的でした。
- 必要書類(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など)を収集
- 法務局の窓口で申請書様式を入手、または法務局のウェブサイトからダウンロード
- 申請書に必要事項を手書きまたはパソコンで入力し印刷
- 収集した書類と印刷した申請書、登録免許税分の収入印紙を添えて、管轄の法務局の窓口に提出
- 補正(書類に不備があった場合の訂正)のために再び法務局へ出向く可能性
- 登記完了後、登記識別情報通知や登記完了証を受け取りに法務局へ出向く
この方法の大きな課題は、「時間」と「場所」の制約でした。
- 法務局が開いている平日日中にしか窓口での提出・相談ができない。
- 管轄の法務局が遠方の場合、移動時間と交通費がかかる。
- 書類の量が膨大で、書き間違いのリスクがある。
- 窓口での待ち時間が発生する可能性がある。
これらの物理的な制約が、相続人の負担となっていました。
オンライン申請の登場
これに対し、オンライン申請はこれらの制約を大きく緩和するものです。
オンライン申請では、インターネットを通じて登記申請に関する情報を法務局に送信します。これにより、
- 法務局に出向く必要がなくなる(原則)
- 場所を選ばず、インターネット環境があればどこからでも申請できる
- 申請データの作成は夜間や休日でも可能(送信は稼働時間内)
といったメリットが生まれます。
ただし、「オンライン申請=紙が一切不要」というわけではありません。収集した戸籍謄本などの添付書類は、原則として別途郵送または持参する必要があります。完全にデジタルデータのみで完結するわけではない点は理解しておきましょう。(一部、電子署名で代替できる書類もありますが、相続登記においては紙の書類が必須となるケースが多いです。)
相続登記をオンラインで行うメリット
では、相続登記のオンライン申請には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
1. 時間と場所にとらわれない
最大のメリットは、これまでの紙申請の最大の課題であった時間と場所の制約が大幅に軽減される点です。
- 法務局の窓口が開いていない夜間や休日でも、自宅や好きな場所で申請データの作成ができます。
- 申請データの送信は、法務局の稼働時間内(原則平日8時30分~21時)であればいつでも可能です。仕事終わりや休日でも手続きを進められます。
- 管轄の法務局が遠方でも、移動することなく申請できます。
これにより、多忙な方や遠方に住んでいる方にとって、手続きのハードルが大きく下がります。
2. 申請用総合ソフトで効率的に申請書を作成できる
オンライン申請では、法務局が提供する無料のソフトウェア「申請用総合ソフト」を使用します。
このソフトには、申請書様式が組み込まれており、画面の案内に従って入力していくことで、必要事項の記載漏れなどを減らすことができます。また、一度入力した不動産の情報などを再利用することも可能です。
手書きやワードでゼロから作成するよりも、効率的に正確な申請書データを作成しやすくなります。
3. 申請状況をオンラインで確認できる
申請用総合ソフトを利用することで、提出した申請の処理状況をオンライン上で確認できます。「今、自分の申請がどうなっているんだろう?」という不安を軽減できます。
4. 登録免許税の納付もオンラインで可能
登記には登録免許税がかかりますが、これもインターネットバンキングなどを利用してオンラインで納付できます。法務局に収入印紙を買いに行く手間が省けます。
5. 補正指示もオンラインで受け取れる(場合がある)
申請内容に軽微な不備があった場合、補正の指示をオンラインで受け取り、オンラインで対応できるケースがあります。これにより、法務局への出頭回数を減らせる可能性があります。
このように、オンライン申請は従来の紙申請に比べて、**利便性、効率性、時間・場所の自由度**において大きなメリットがあると言えます。
相続登記をオンラインで行うために必要な準備
メリットを享受するためには、オンライン申請ならではの準備が必要です。主な準備項目は以下の通りです。
1. パソコンとインターネット環境
申請用総合ソフトをインストールし、インターネットに接続できるパソコンが必要です。ソフトの動作環境(OSなど)を確認しておきましょう。
2. 申請用総合ソフトのインストール
法務局のウェブサイトから「申請用総合ソフト」をダウンロードし、お使いのパソコンにインストールします。利用マニュアルも併せてダウンロードし、操作方法を確認しましょう。
3. 電子証明書とカードリーダー
オンライン申請では、申請者が本人であることを証明するために「電子署名」が必要です。この電子署名を行うために、電子証明書が格納された媒体と、それを読み取るためのカードリーダーが必要になります。
個人の方が利用する場合、最も一般的なのはマイナンバーカード(個人番号カード)に格納された署名用電子証明書を利用する方法です。マイナンバーカード方式の場合、ICカードリーダーライターが必要になります。法務局のウェブサイトで動作確認済みの機種を確認しましょう。
その他、商業登記に利用する電子証明書など、他の種類の電子証明書も利用できる場合がありますが、個人の方が相続登記で利用する際はマイナンバーカードが現実的な選択肢となります。
4. 必要書類の収集とスキャン
オンライン申請であっても、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)など、相続登記に必要な書類を収集する必要があります。これらの書類は、原本を別途郵送または持参する必要がある場合が多いですが、申請用総合ソフトに添付するために、スキャンしてPDFファイルなどの電子データにする必要があります。
高性能なスキャナーや複合機があると便利ですが、スマートフォンのスキャンアプリでも対応できる場合があります。ただし、文字が鮮明に読み取れる解像度でスキャンすることが重要です。
5. 不動産の情報
申請する不動産の正確な情報(所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積など)が必要です。これらの情報は、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税の納税通知書などで確認できます。
6. 登録免許税の納付準備
オンラインで納付する場合、インターネットバンキングの準備をしておきましょう。
このように、オンライン申請には従来の紙申請には不要だったIT関連の準備が必要です。「パソコンにあまり慣れていない」「電子証明書って何?」という方にとっては、この準備段階が最初のハードルとなるかもしれません。
相続登記オンライン申請の具体的な流れ
必要な準備が整ったら、いよいよオンライン申請の手続きです。大まかな流れは以下のようになります。
ステップ1:申請用総合ソフトの起動と申請書作成
申請用総合ソフトを起動し、新規の申請データを作成します。相続登記を選択し、画面の案内に従って、申請人(相続人)の情報、被相続人の情報、不動産の情報を入力していきます。
不動産の情報は、登記簿謄本を見ながら正確に入力しましょう。持分での相続の場合は、それぞれの相続人の持分も正確に記載します。
ステップ2:添付書類の登録
収集しスキャンしておいた戸籍謄本や遺産分割協議書などの添付書類を、申請用総合ソフトに登録します。PDFファイルなどを指定された形式でソフトに取り込みます。
※繰り返しになりますが、これらの書類の原本は後日法務局に提出する必要があります。
ステップ3:電子署名を行う
作成した申請データに対し、電子署名を行います。マイナンバーカードとカードリーダーを使って、申請者本人が電子署名を行います。この電子署名によって、申請データが申請者本人の意思に基づいて作成されたものであることが証明されます。
申請人が複数いる場合は、原則として申請人全員の電子署名が必要です。</ただし、司法書士などの代理人に依頼する場合は、代理人の電子署名のみで済みます。
ステップ4:登録免許税額の入力と納付方法の選択
申請する不動産の固定資産評価額などに基づき、登録免許税額を計算し、ソフトに入力します。納付方法として、オンライン納付(インターネットバンキング)を選択します。
ステップ5:申請データを法務局へ送信
全ての入力と添付書類の登録、電子署名が終わったら、申請データを法務局へ送信します。送信できるのは、法務局の稼働時間内(平日8時30分~21時)です。
ステップ6:登録免許税の納付
申請データ送信後、申請用総合ソフトからインターネットバンキングのサイトへアクセスし、登録免許税を納付します。納付が完了しないと、申請は受け付けられません。
ステップ7:添付書類の提出
申請データを送信し、登録免許税の納付が完了したら、添付書類の原本を管轄の法務局へ提出します。提出方法は、郵送または持参です。申請用総合ソフトで作成した「添付書類送付書」を同封すると、法務局での処理がスムーズになります。
ステップ8:法務局での審査と補正
法務局で申請内容と添付書類の審査が行われます。内容に不備があった場合は、法務局から補正指示があります。補正指示は、申請用総合ソフトを通じて行われる場合と、電話で行われる場合があります。指示に従って内容を訂正または書類を追加提出します。
ステップ9:登記完了と完了書類の取得
登記が完了すると、申請用総合ソフトに登記完了の通知が届きます。登記識別情報通知(パスワードのようなもの)や登記完了証は、登記申請時に指定した方法(法務局での受取または郵送)で受け取ります。
このように、オンライン申請はデータの作成・送信部分はオンラインで行えますが、添付書類の原本提出は別途必要となり、完全に自宅で完結するわけではない点がポイントです。
オンライン申請の注意点・デメリット
メリットが多いオンライン申請ですが、いくつか注意しておきたい点、デメリットと感じる可能性がある点もあります。
1. 申請用総合ソフトの操作にある程度の慣れが必要
申請用総合ソフトは、登記申請という専門的な手続きに対応するためのソフトウェアです。初めて使用する方にとっては、用語や操作方法に戸惑うことがあるかもしれません。マニュアルをよく読んだり、法務局のウェブサイトにある操作説明を確認したりする時間が必要です。
2. 電子証明書やカードリーダーの準備が必要
先述の通り、マイナンバーカードなどの電子証明書とカードリーダーの準備、設定が必要です。これらの機器や設定に不慣れな場合は、ここが最初の関門となります。
3. 書類のスキャン作業が必要
必要な全ての書類を正確にスキャンし、指定された形式で保存する作業が必要です。書類が多い場合や、スキャナーがない場合は手間がかかります。
4. 添付書類の原本提出は必要
申請データはオンラインで送信できますが、戸籍謄本などの添付書類の原本は、申請後に法務局に郵送または持参する必要があります。完全に「自宅から一歩も出ずに完了」とはならない点に注意が必要です。
5. 相続関係や不動産が複雑な場合は難しい
相続人が多数いる、代襲相続が発生している、対象となる不動産が複数ある、遺産分割協議が複雑など、相続関係や不動産の情報が複雑なケースでは、オンライン申請書の作成も難しくなります。記載ミスや添付書類の不足が生じるリスクが高まります。
6. 補正対応の手間
申請内容に不備があった場合の補正対応も、オンラインまたは電話で行う必要があります。法務局からの指示を正確に理解し、対応する必要があります。
これらのデメリットを踏まえると、オンライン申請はITツールに抵抗がなく、比較的シンプルな相続ケースに適していると言えるでしょう。
自分でオンライン申請 VS 司法書士に依頼
相続登記をオンラインで行う場合、「自分で申請用総合ソフトを使ってオンライン申請する」方法と、「司法書士に依頼して、司法書士がオンライン申請する」方法があります。
それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 項目 | 自分でオンライン申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 手続きを行う人 | 相続人本人 | 司法書士(相続人の代理人として) |
| オンライン申請の方法 | 申請用総合ソフトを使用 | 司法書士が専門のソフトを使用(多くはオンライン申請) |
| 書類収集・作成 | 全て自分で行う | 基本的には司法書士が行う(必要な書類の指示はあり) |
| メリット | 費用を安く抑えられる(登録免許税と実費のみ) 自分のペースで進められる |
専門家が全て行ってくれるので手間がかからない 正確かつスムーズに手続きが進む 書類の準備や作成のミスがない জটিলなケースにも対応可能 遺産分割協議書の作成なども任せられる |
| デメリット | 時間と手間がかかる ITスキルや登記の知識が多少必要 書類収集や作成のミスをするリスクがある জটিলなケースだと挫折しやすい |
司法書士への報酬が発生する |
| 費用 | 登録免許税 + 書類取得費用 + 電子証明書・カードリーダー費用(初期投資) | 登録免許税 + 書類取得費用 + 司法書士への報酬 |
「自分でオンライン申請」は、費用を最小限に抑えたい、時間に余裕がある、パソコン操作や調べものが得意、相続関係がシンプル、という方に向いています。
一方、「司法書士に依頼」は、手続きに時間や手間をかけたくない、手続きに自信がない、複雑な相続ケースである、仕事や家事で忙しい、という方におすすめです。
多くの司法書士は、現在ではオンライン申請を積極的に利用しています。つまり、司法書士に依頼することは、専門家によるスムーズなオンライン申請のメリットを享受することにつながります。
どちらの方法を選択するかは、ご自身の状況や考え方によって異なります。かかる費用と、ご自身の時間や労力、専門知識の必要性を天秤にかけて検討すると良いでしょう。
まとめ:相続登記オンライン申請を賢く選択しよう
相続登記のオンライン申請は、従来の紙申請に比べて多くのメリットがあり、特に時間や場所にとらわれずに手続きを進めたい方にとって画期的な方法です。
ただし、完全に紙が不要になるわけではなく、必要書類の収集・スキャン、電子証明書の準備、申請用総合ソフトの操作など、オンラインならではの準備と作業が必要になります。
相続関係や不動産がシンプルであれば、ご自身でオンライン申請に挑戦するのも良いでしょう。費用を抑えることができます。
しかし、手続きに不安がある場合や、相続ケースが複雑な場合は、無理せず司法書士に依頼することを検討しましょう。司法書士はオンライン申請にも精通しており、正確かつスムーズな手続きをサポートしてくれます。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、放置することによるリスクが高まりました。いずれにしても、不動産を相続した際には、できるだけ早く相続登記を行うことが大切です。
オンライン申請という新しい選択肢を知り、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、相続登記を無事に完了させてください。
この記事が、あなたの相続手続きの一助となれば幸いです。
※本記事は2025年5月時点の情報に基づいていますが、登記制度やオンライン申請の方法は改正される可能性があります。手続きを行う際は、必ず最新の法務省の情報を確認するか、専門家にご相談ください。
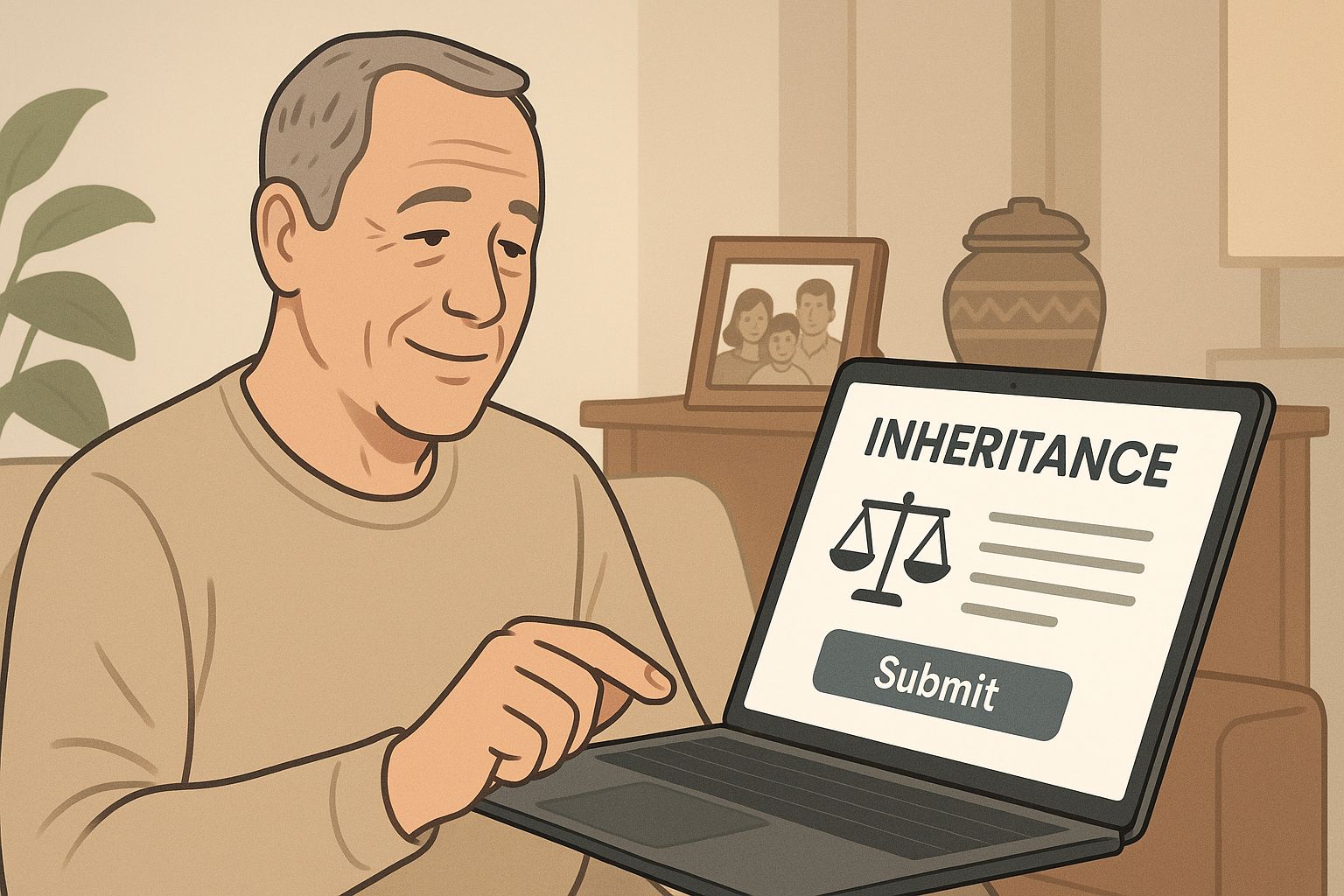


コメント