「終活」と聞くと、少し気が重いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは残りの人生をより良く生きるための前向きな準備であり、そして、大切な家族が将来困らないように、あなたの想いをきちんと形にして残すための行動です。
その「終活」において、最も重要な要素の一つが「遺言書」です。遺言書は、あなたの死後、あなたの財産をどのように分けたいか、誰に何を託したいかといった、あなたの最後の意思を明確に伝えるための、法的に有効な文書です。
「でも、遺言書って難しそう…」「どんな種類があるの?」「自分で書けるの?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言書に関する基本的な知識を、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。特に、知っておくべき「遺言書の種類」と、その「法的効力」に焦点を当て、あなたが後悔しない終活を進めるための一助となることを目指します。
この記事を読み終える頃には、遺言書がなぜ必要なのか、自分にはどのような遺言書が合っているのか、そしてどのように作成すれば良いのか、その全体像が見えてくるはずです。
さあ、あなたの未来へのメッセージを形にする旅を始めましょう。
なぜ、遺言書は必要なのでしょうか?
「うちにはそんなに財産がないから、遺言書なんて関係ない」「家族仲が良いから大丈夫」そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書は、財産の多寡や家族仲の良し悪しに関わらず、作成しておくことを強くお勧めします。
1. 遺産を巡る「争族」を防ぐ
最も大きな理由は、残された家族が「争族(相続を巡る争い)」に巻き込まれるのを防ぐためです。
故人が遺言書を残さなかった場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。家族仲が良くても、いざお金や不動産が絡むと、それまで見えなかった感情が表面化し、骨肉の争いに発展してしまうケースは後を絶ちません。
故人の意思が明確に示された遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要となり、スムーズに手続きを進めることができます。これは、残された家族にとって何よりの配慮と言えるでしょう。
2. あなたの「想い」を実現する
法律で定められた相続分(法定相続分)は、必ずしも故人の意思を反映するものではありません。
「長年連れ添った配偶者に全財産を渡したい」「お世話になった人に財産の一部を遺贈したい」「特定の事業を継ぐ子どもに多めに渡したい」「社会貢献のために寄付したい」など、あなたの特定の想いや願いがある場合、それを実現するためには遺言書が不可欠です。
遺言書がなければ、あなたの財産は基本的に法定相続分に従って分けられることになり、あなたの真の想いは叶えられない可能性が高くなります。
3. 手続きをスムーズに進める
遺言書がない場合、遺産分割協議がまとまるまで、相続手続き(預貯金の引き出し、不動産の名義変更など)を進めることができません。協議が難航すればするほど、手続きは滞り、家族に負担をかけることになります。
有効な遺言書があれば、それに従って速やかに手続きを開始できます。特に、遺言執行者が指定されていれば、相続人自身が煩雑な手続きを行う必要がなくなり、大きな負担軽減となります。
このように、遺言書は単なる財産分与の指示書ではなく、残された家族への最後の「ラブレター」であり、彼らが平穏に暮らしていくための「道しるべ」となるものなのです。
遺言書でできること
遺言書には、財産の分け方だけでなく、様々な内容を盛り込むことができます。民法で定められている、遺言書で効力が認められる主な事項を見てみましょう。
- 相続分の指定・指定の委託:法定相続分とは異なる割合で、各相続人の相続分を指定できます。
- 遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止:具体的な財産を誰に相続させるかを指定したり、一定期間(最長5年)遺産分割を禁止したりできます。
- 相続人以外への遺贈(いぞう):法定相続人ではない、友人、内縁の妻、孫、お世話になった人、団体などに財産を分け与えることができます。
- 相続人・受遺者(じゅいしゃ)の負担付遺贈:財産を与える代わりに、特定の義務(例:「ペットの世話をすること」を条件に財産を遺贈する)を課すことができます。
- 遺言執行者の指定・指定の委託:遺言の内容を実現するための手続きを行う人(遺言執行者)を指定できます。
- 子の認知:婚姻関係にない女性との間に生まれた子を、遺言によって自分の子と認めることができます。
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定:未成年の子どもがいる場合、親権者がいない、または親権を行うことができない場合に、未成年後見人やその監督人を指定できます。
- 推定相続人の廃除・取消し:虐待や重大な侮辱など、一定の事由がある推定相続人から、遺言によって相続権を剥奪できます。また、一度廃除した相続人の相続権を戻すこともできます。
- 生命保険金受取人の変更:契約によっては、遺言で生命保険金の受取人を変更できる場合があります。
- 一般社団法人・一般財団法人の設立:遺言によって、ご自身の財産を基に法人を設立できます。
- お墓や仏壇の祭祀主宰者の指定:代々受け継がれるお墓や仏壇など(祭祀財産)を承継する人を指定できます。
- 付言事項(ふげんじこう):法的な効力はありませんが、遺言書に書ききれなかった家族への感謝の気持ち、遺産分割に関する理由、葬儀や供養に関する希望などを自由に書き記すことができます。これが残された家族の納得や理解につながり、争いを防ぐ上で非常に重要な役割を果たします。
このように、遺言書は単に財産を分配するだけでなく、あなたの人生の集大成として、様々な想いを託すことができるパワフルなツールなのです。
知っておくべき遺言書の「種類」
日本で法的に認められている遺言書には、いくつかの種類があります。中でも一般的で、私たちが知っておくべきなのは以下の3つの方式です。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
最も手軽に作成できる遺言書です。文字通り、遺言者本人が「自筆」で作成します。
作成方法・要件
- 遺言書の「全文」、作成した「日付」、遺言者の「氏名」を、遺言者本人が「自筆」で書く必要があります。
- 押印が必要です(認印でも可)。
- 【重要】財産目録については、パソコン等で作成し、添付することが認められています(ただし、財産目録の各ページに署名・押印が必要です)。それ以外の本文は、必ず自筆で書かなければなりません。
- 証人は不要です。
- 費用はほとんどかかりません(用紙代、インク代程度)。
メリット
- いつでも、どこでも、誰にも知られずに一人で手軽に作成できます。
- 費用がほとんどかかりません。
- 何度でも書き直しが自由にできます。
デメリット
- 形式不備により無効となるリスクが高いです。特に日付や押印漏れ、加筆修正の方法などに注意が必要です。
- 内容が不明確だったり、曖昧だったりすると、後に争いの原因となる可能性があります。
- 紛失したり、発見されなかったり、あるいは意図的に隠されたりするリスクがあります。
- 家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きが必要です(後述)。この手続きには時間と手間がかかります。法務局で保管している場合は検認が不要となります。
2020年7月10日施行の変更点:自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言のデメリットを補うために、「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。これは、作成した自筆証書遺言書を法務局に預けることができる制度です。
- メリット:
- 法務局が原本を保管するため、紛失や改ざん、隠匿の心配がありません。
- 方式の確認(一部)が行われるため、形式不備による無効のリスクを減らせます(内容の有効性を保証するものではありません)。
- 家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。
- 相続発生後、相続人等が遺言書が保管されているかどうかを検索できます。
- デメリット:
- 法務局に予約して出向く必要があります。
- 手数料がかかります(保管申請時)。
- 遺言の内容に関する相談には乗ってもらえません。あくまで保管と形式確認の制度です。
この制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットのかなりの部分を解消できますが、遺言の内容自体をしっかり検討する必要がある点は変わりません。
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証役場で、公証人が遺言者の指示を聞き取り、作成する遺言書です。最も安全で確実な方法と言われています。
作成方法・要件
- 証人2人以上の立ち会いが必要です。
- 遺言者が公証人に遺言の内容を伝えます。
- 公証人が遺言者の話に基づいて遺言書を作成します。
- 作成された遺言書を、遺言者、証人、公証人が確認し、それぞれ署名・押印します。
- 原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。
- 費用がかかります(遺産の価額に応じて変動します)。
メリット
- 公証人が法律の専門家として関与するため、形式不備による無効のリスクが極めて低いです。
- 内容についても、公証人が専門的な見地から助言をしてくれるため、不明確な点や法的な問題点を解消できます。
- 公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
- 家庭裁判所での「検認」手続きが不要です。相続発生後、すぐに遺言の内容を実現する手続きに移れます。
- 病気などで筆記が困難な場合でも作成可能です(公証人が代筆します)。
デメリット
- 費用がかかります。
- 証人2人以上の立ち会いが必要です。身近な人に頼むか、専門家(弁護士、司法書士など)に依頼する必要があります。
- 公証役場に出向く必要があります(病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうことも可能ですが、その場合は費用が割増しになります)。
- 遺言の内容を公証人や証人に知られることになります(秘密証書遺言に比べるとプライバシーは低くなります)。
確実性と安全性を最優先するならば、公正証書遺言が最もお勧めできる方式です。
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言書の内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で証明してもらう方式です。日本ではあまり利用されていません。
作成方法・要件
- 遺言者自身または第三者が遺言書を作成します(自筆でもパソコンでも可)。署名は遺言者自身が行う必要があります。
- 遺言書に署名・押印した上で、これを封筒に入れ、遺言書に用いた印鑑で封印します。
- その封書を公証役場に持参し、公証人および証人2人以上の前に提出し、自分の遺言書であること、その筆者の氏名・住所を申述します。
- 公証人が封紙に日付と遺言者の申述を記載し、遺言者と証人とともに署名・押印します。
メリット
- 遺言書の内容を誰にも知られずに済みます。
- 遺言書の存在を公的に証明してもらえます。
デメリット
- 遺言書の内容そのものが法律の要件を満たしているかどうかの確認は受けられません。内容の不備により無効となるリスクがあります。
- 家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
- 封筒の開封方法によっては、遺言書が無効となる可能性があります。
- 作成に手間がかかる割に、メリットが少ないため、利用は稀です。
遺言書の「法的効力」とは?
遺言書が「法的効力を持つ」とは、簡単に言えば「遺言書に書かれた内容が、法的に有効となり、実現される」ということです。
しかし、遺言書を作成すれば、自動的に全ての項目が実現するわけではありません。法的な効力が認められるためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
1. 法律で定められた「方式」に従っていること
前述の通り、遺言書は民法で厳格に方式が定められています。自筆証書遺言であれば全文自筆であること、日付、氏名、押印があること。公正証書遺言であれば証人の立ち会いがあることなど、その方式に一つでも不備があると、その遺言書は無効となってしまいます。
これが、自筆証書遺言が形式不備で無効になりやすいと言われる所以です。法務局の保管制度を利用するか、専門家(弁護士、司法書士)にチェックを依頼することをお勧めします。
2. 遺言者に「遺言能力」があること
遺言を作成する時点で、遺言者が正常な判断能力を持っている必要があります。認知症などで自分の財産状況や、誰に何を相続させるかを理解できない状態での遺言は無効となる可能性があります。
ご自身の判断能力が確かなうちに作成することが重要です。判断能力に不安がある場合は、公正証書遺言を作成する際に医師の診断書を準備するなど、慎重な対応が必要です。
3. 遺言の内容が「法律に違反しない」こと
遺言の内容が公序良俗に反する場合や、強行法規(法律で定められた、当事者の意思に関わらず強制的に適用されるルール)に違反する場合は、その部分の遺言は無効となることがあります。
例えば、特定の相続人に対して「絶対に遺留分を請求しないこと」と遺言書に記載したとしても、遺留分は法律で認められた権利であるため、この記載には法的な効力はありません(ただし、付言事項として、遺留分を請求しないようにお願いするメッセージを添えることは有効です)。
また、遺留分を侵害する内容の遺言も、それ自体は無効にはなりませんが、遺留分権利者から「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を受ける可能性があります。
遺留分(いりゅうぶん)とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母))に最低限保障されている遺産の取り分のことです。故人が遺言書で「全財産を特定の第三者に遺贈する」と書いても、遺留分権利者はその遺贈を受けた人に対して、遺留分に相当する金銭を請求する権利があります。
遺言書を作成する際には、この遺留分を考慮に入れることが、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。遺留分について不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
遺言書の「検認(けんにん)」手続きとは?
自筆証書遺言(法務局で保管されているものを除く)や秘密証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを経なければなりません。
検認とは、相続人全員の立ち会いのもと、遺言書の形式や状態を確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言書の内容の有効性を判断するものではありません。
この検認を経ずに遺言書を開封したり、遺言の内容を実現したりすると、5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管されているため、検認は不要です。これが公正証書遺言の大きなメリットの一つです。
どの種類の遺言書を選ぶべきか?
結局のところ、どの種類の遺言書を選べば良いのでしょうか。これは、遺言者の状況や重視することによって異なります。
- 手軽さ・費用を最優先するなら → 自筆証書遺言(ただし、法務局の保管制度利用を強く推奨)
- 確実性・安全性を最優先し、費用や手間がかかっても良いなら → 公正証書遺言
- 遺言の内容を絶対に秘密にしたいが、検認の手間がかかることを許容できるなら → 秘密証書遺言(内容は別途専門家に確認してもらう必要あり)
一般的には、無効のリスクが低く、検認も不要な公正証書遺言が最も推奨されます。遺産が複雑でない場合や、とにかく費用をかけたくない場合は、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も有効な選択肢となります。
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)の役割
遺言書を作成する際に、ぜひ検討していただきたいのが「遺言執行者」の指定です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人のことです。具体的には、相続財産の調査・目録作成、預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更、遺贈を受けた人への財産引渡し、相続人の廃除手続きなどを行います。
遺言執行者を指定しない場合、これらの手続きは相続人全員または相続人のうちの一部の人が行わなければならず、非常に手間と時間がかかります。
遺言執行者を指定しておけば、その人が単独でこれらの手続きを進めることができるため、相続人の負担を大きく減らし、遺言の内容をスムーズかつ確実に実現できます。
遺言執行者には、相続人でも第三者でも、法人でもなることができます。相続人のうちの誰かを指定することも可能ですが、より中立公平な立場から確実に執行してもらうためには、弁護士や司法書士などの専門家、または信託銀行などに依頼することも有力な選択肢です。
遺言書はいつでも「撤回」できる
一度作成した遺言書も、その時の状況や心境の変化に合わせて、いつでも撤回したり、内容を変更したりすることができます。
撤回や変更の方法は、主に以下の通りです。
- 新しい遺言書を作成する:内容が矛盾する複数の遺言書がある場合、日付が最も新しい遺言書が優先されます。新しい遺言書で、以前の遺言書の内容と矛盾する部分や、以前の遺言書を全て撤回する旨を記載すれば、以前の遺言書は無効になります。
- 遺言書を破棄する:以前作成した遺言書を、撤回する意思を持って破り捨てるなど物理的に破棄することで、その遺言書を撤回できます。ただし、意図せずに誤って破棄した場合は撤回とはなりません。
- 遺贈した財産を処分する:遺言書で「〇〇に土地Aを遺贈する」と書いていたが、その土地Aを遺言書作成後に売却した場合など、遺贈の対象とした財産を遺言者自身が処分したときは、その処分行為と矛盾する遺言の部分は撤回されたものとみなされます。
遺言書は、一度作ったら終わりではなく、ご自身の状況に合わせて見直し、必要に応じて変更していくことが大切です。
遺言書作成で失敗しないためのポイント
せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまったり、かえって争いの原因になってしまったりしたら元も子もありません。失敗しないためのポイントをいくつかご紹介します。
- 法定方式を正確に守る:特に自筆証書遺言の場合、日付の記載方法一つで無効になることがあります。細部まで法律の要件を満たしているか、十分確認しましょう。法務局の保管制度を利用するか、専門家に見てもらうのが最も安全です。
- 内容は具体的に、明確に:「自宅を長男に」だけでなく、「○○市△△町1-2-3の土地と、その上にある建物を、長男である山田太郎に相続させる」のように、誰にどの財産をどのように渡すのか、具体的に特定できるように記載しましょう。
- 遺留分に配慮する:遺留分を無視した遺言は、後に遺留分侵害額請求を招き、かえってトラブルになる可能性が高いです。遺留分権利者の存在と、その割合を理解した上で遺言の内容を検討しましょう。
- 付言事項を活用する:法的な効力はありませんが、遺産分割の理由や家族への感謝の気持ちを書き添えることで、残された家族が遺言者の真意を理解し、納得してくれやすくなります。
- 保管場所を伝え、遺言書の存在を知らせておく:遺言書を作成しても、誰もその存在や保管場所を知らなければ、相続発生後に発見されない可能性があります。信頼できる家族や専門家に、遺言書を作成したことと、保管場所を伝えておきましょう。公正証書遺言や法務局の保管制度を利用すれば、この心配はありません。
- 定期的に見直す:家族構成の変化(出生、死亡、結婚、離婚)、財産の変動、法改正などにより、以前作成した遺言書が現状に合わなくなることがあります。3~5年を目安に定期的に見直しを行いましょう。
専門家への相談を検討しましょう
遺言書は、あなたの最後の意思を確実に実現するための重要なツールです。しかし、その作成には法的な知識が不可欠であり、不備があるとせっかくの遺言書が無効になってしまうリスクも伴います。
特に、以下のようなケースでは、専門家(弁護士、司法書士、税理士、公証人役場など)に相談することをお勧めします。
- 財産の種類や金額が多い、複雑である
- 相続人が多い、または相続人以外の人に財産を分け与えたい
- 相続人の中に、行方不明者や連絡が取りにくい人がいる
- 特定の相続人に、通常より多くまたは少なく財産を与えたい
- 遺留分が心配である
- 事業承継を考えている
- 遺言執行者を指定したいが、誰が良いか分からない
- とにかく正確で確実な遺言書を作成したい
- 自筆証書遺言を作成したが、形式や内容に不安がある
専門家は、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、法的な観点から最適な遺言書の内容や方式を提案してくれます。また、公正証書遺言の作成をサポートしたり、自筆証書遺言のチェックを行ったりすることも可能です。
専門家への依頼には費用がかかりますが、それによって遺言書の無効を防ぎ、後の家族間の争いを回避できるのであれば、決して高い投資ではないはずです。
まとめ:遺言書は未来への「安心」と「想い」を届けるもの
遺言書は、あなたの死後、残された家族が相続手続きで困らないように、そして何より、あなたの最後の「ありがとう」や「想い」を形として伝えるための、非常に大切な手段です。
この記事では、遺言書の必要性、できること、主な3つの種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の特徴、そして法的効力や注意点について詳しく解説しました。
どの種類の遺言書を選ぶにしても、大切なのは「自分の想いをしっかりと整理し、それを法的に有効な形で残す」ことです。
遺言書作成は、決して後ろ向きな行為ではありません。むしろ、残りの人生を安心して過ごし、大切な家族の未来を守るための、前向きな「終活」の第一歩です。
この記事が、あなたが遺言書について理解を深め、最初の一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。もし、さらに詳しく知りたい点や、個別の状況に関する不安があれば、迷わず専門家にご相談ください。
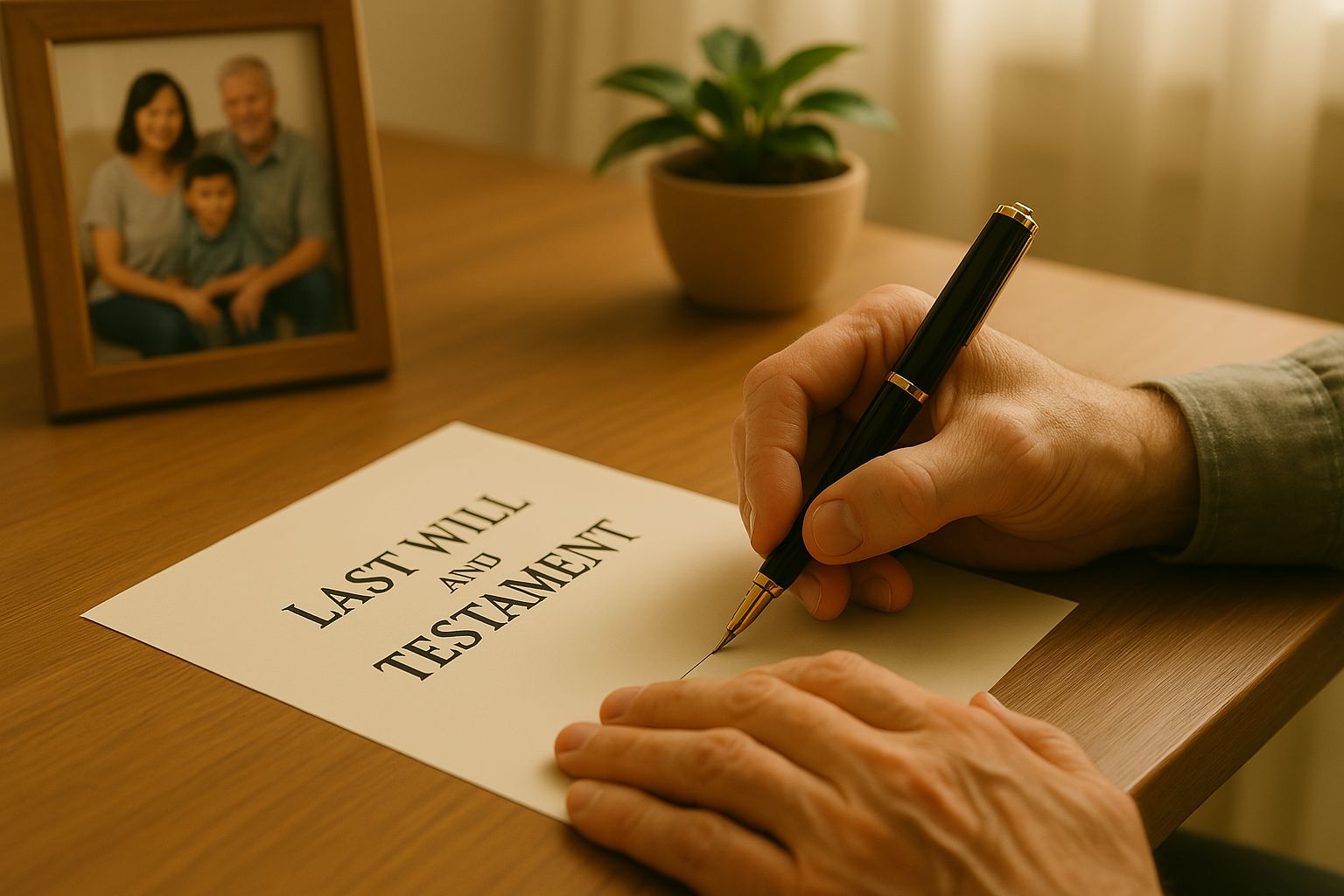


コメント