大切なご家族が亡くなられた。心落ち着かない中で直面するのが「相続」の問題です。故人が遺してくれた財産を受け継ぐことは、多くの場合、故人の想いと共にありがたく受け取るものかもしれません。
しかし、相続財産はプラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけとは限りません。時には、借金や未払いの税金、連帯保証債務といった「マイナスの財産」が含まれていることもあります。そして、そのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続することが、かえってあなたの生活を苦しめる可能性も出てきます。
そんな時に検討すべきなのが「相続放棄」です。
相続放棄は、「自分は初めから相続人ではなかった」とみなされる強力な手続きです。しかし、これには厳格なルールと期限があり、安易に判断すると取り返しのつかない事態を招くこともあります。
このブログ記事では、相続放棄をすべきかどうかの判断基準から、具体的な手続き方法、注意点までを網羅的に、分かりやすく解説します。今まさに相続のことで悩んでいる方、将来の相続に備えて知識を得たいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
相続放棄とは?「選ばない」という選択肢
相続放棄とは、相続人が、故人の一切の財産(プラスの財産、マイナスの財産を含む)を相続する権利を放棄する意思表示です。これは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されることによって正式に成立します。
相続放棄が受理されると、その相続人は、法律上、最初から相続人でなかったことになります。つまり、故人のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がなくて済む代わりに、受け取ることもできなくなります。
「相続しない」という選択肢があることは、特に故人に多額の借金があった場合などには、相続人自身の生活を守るための重要な手段となります。
なぜ相続放棄を検討するのか?主な理由
相続放棄を検討するケースは様々ですが、代表的な理由は以下の3つです。
理由1:故人に多額の借金があった場合
これが最も一般的な理由です。故人の借金は、相続人が引き継ぐ義務があります。相続財産に借金がプラスの財産を明らかに上回る場合、相続してしまうと、自分の財産から借金を返済しなければならなくなります。このような状況を避けるために、相続放棄を選択します。
理由2:相続財産が少なく、遺産分割協議に関わりたくない場合
相続財産がほとんどない場合や、特定の相続人(例えば配偶者)に全ての財産を相続させたい場合などにも、相続放棄が利用されることがあります。特に、複数の相続人がいる場合、たとえ財産が少なくても遺産分割協議は必要になります。話し合いがまとまらないことによる精神的な負担や手間を避けたいという理由で、相続放棄を選ぶ人もいます。
理由3:特定の相続人に財産を集中させたい場合
例えば、父が亡くなり、相続人が母と子の場合、子が相続放棄することで、母が単独で全ての財産を相続できます。これにより、その後の手続き(不動産の名義変更など)が簡略化されるというメリットがあります。
相続放棄すべきか?判断のための重要なステップ
相続放棄は一度行うと原則として撤回できません。そのため、慎重な判断が必要です。以下のステップを踏んで、ご自身の状況を正確に把握しましょう。
ステップ1:相続財産(プラス・マイナス両方)の調査
まずは、故人にどのような財産があったのかを正確に把握することから始まります。
- プラスの財産:預貯金、不動産(土地、建物)、株式、投資信託、自動車、貴金属、骨董品、著作権など
- マイナスの財産:借金(カードローン、消費者金融、住宅ローン、自動車ローン)、未払いの税金、未払いの公共料金、家賃滞納、連帯保証債務など
特にマイナスの財産は、プラスの財産ほど目に見えにくいため、注意深く調査する必要があります。
マイナス財産の調査方法:
- 郵便物や契約書の確認:金融機関や消費者金融からの督促状、借用書、保証契約書などがないか確認します。
- 信用情報機関への照会:故人が生前に利用していた可能性のある信用情報機関(日本では主にCIC、JICC、KSC)に情報開示請求を行うことで、借入状況や保証債務の有無を確認できる場合があります。(ただし、相続人からの開示請求には制限がある場合がありますので、事前に確認が必要です。)
- 金融機関への問い合わせ:故人が利用していた可能性のある金融機関に、借入の有無を確認します。
- 固定資産税納税通知書:不動産の有無を確認できます。
- 税務署からの通知:未払い税金の有無を示唆することがあります。
これらの調査は、原則として相続開始を知った日(通常は故人の死亡日)から3ヶ月以内に行う必要があります。
ステップ2:財産全体の価値を評価し、差額を確認する
プラスの財産とマイナスの財産をリストアップし、それぞれのおおよその価値を評価します。そして、「プラスの財産の合計」と「マイナスの財産の合計」を比較します。
- プラス > マイナス:相続するメリットがある可能性が高い
- プラス < マイナス:相続放棄を検討すべき可能性が高い
- プラス = マイナス、または不明:慎重な判断が必要
不動産の評価は専門家(不動産鑑定士や税理士)に依頼したり、固定資産税評価額を参考にしたりします。借金は残高証明書を取り寄せて正確な額を確認します。
ステップ3:相続順位と次順位の相続人への影響を考慮する
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったことになるため、相続権が次順位の相続人に移ります。
例えば、故人に配偶者と子がいる場合、第一順位の相続人は配偶者と子です。子が相続放棄すると、子の相続権は無くなり、子が複数いれば残りの子だけが、子が一人もいなくなれば第二順位の相続人(故人の父母や祖父母などの直系尊属)が相続人となります。
さらに、第二順位の相続人全員が相続放棄した場合、第三順位の相続人(故人の兄弟姉妹や甥姪)が相続人となります。
あなたが相続放棄することで、それまで相続に関係なかった親族に相続権が移り、思わぬ負担をかけてしまう可能性もあります。相続放棄を検討する際は、次順位の相続人にもその旨を伝え、よく話し合うことが望ましいでしょう。
ステップ4:熟慮期間(3ヶ月)と「法定単純承認」に注意する
相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時(通常は故人の死亡と、ご自身が相続人になったことを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間中に、相続財産の調査や相続放棄をするかどうかの判断を行います。
【重要】3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として「単純承認」をしたものとみなされます。これを「法定単純承認」といいます。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て無限に引き継ぐことです。つまり、多額の借金があったとしても、それを全て相続することになってしまうのです。
ただし、財産状況の調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間を延長できる可能性があります。期間内に調査が終わりそうにない場合は、必ず期間延長の申し立てを行いましょう。
【さらに重要】「法定単純承認」とみなされる行為
熟慮期間中であっても、以下の「法定単純承認」とみなされる行為を行ってしまうと、その時点で単純承認したことになり、原則として相続放棄ができなくなります。
- 相続財産の処分:故人の預貯金を引き出して使用する、故人の車や不動産を売却する、故人の株式を解約するなど。遺産分割協議で自分の取得分を決めたり、相続分を譲渡したりする行為も含まれます。
- 相続財産の隠匿・私的消費・悪意での消費:故人の財産を隠したり、勝手に使ったりすること。
- 相続債務の一部の弁済:故人の借金の一部を支払うこと。(ただし、債権者から請求されてやむを得ず支払った場合など、例外的に単純承認とみなされないケースもありますが、判断が難しいため避けるのが賢明です。)
これらの行為は、「相続する意思がある」とみなされてしまいます。故人の財産には一切手をつけず、安易にお金を使ったり、借金を返済したりしないように十分注意してください。葬儀費用を故人の預貯金から支払うことについては議論がありますが、トラブル防止のためにも、相続人自身の費用で立て替えるか、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
相続放棄の手続き方法:家庭裁判所への申述
相続放棄は、必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することによって行います。大まかな流れは以下の通りです。
ステップ1:必要書類の収集
申述する人や故人との関係性によって必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書:家庭裁判所の窓口やウェブサイトから入手できます。
- 故人の死亡の記載のある戸籍謄本:故人の死亡が確認できるもの。
- 故人の住民票除票または戸籍の附票:故人の最後の住所地を確認するもの。
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本:申述人自身の現在の戸籍謄本。
- その他、申述人と故人との関係性を証明するための戸籍謄本等(故人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続放棄する人が故人の子以外(親、兄弟姉妹など)の場合に関係を証明する戸籍など)
これらの戸籍謄本等は、本籍地の役場で取得します。
ステップ2:相続放棄申述書の作成
申述書には、申述人の氏名、住所、本籍地、生年月日、故人の氏名、死亡日、故人の最後の住所などを記載します。また、「相続放棄をする理由」を記載する欄があります。ここには、「債務超過のため」「相続に関わりたくないため」など、正直な理由を記載します。
ステップ3:家庭裁判所への提出
申述書と必要書類を、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。提出方法は、直接持参するか、郵送でも可能です。
ステップ4:家庭裁判所からの照会(質問状)への回答
申述書を提出すると、家庭裁判所から申述人に対して、本当に相続放棄の意思があるか、法定単純承認に当たるような行為はしていないかなどを確認するための照会書(質問状)が送られてくるのが一般的です。質問事項に正確に回答し、返送します。
ステップ5:相続放棄受理通知書の受け取り
照会書への回答など、家庭裁判所での手続きが終わると、「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」が送られてきます。これが届けば、正式に相続放棄が認められたことになります。
この受理通知書は、債権者への通知など、相続放棄したことを証明する際に必要となる重要な書類です。大切に保管しておきましょう。債権者から請求があった場合に提示することで、相続債務を負わないことを伝えられます。
手続きにかかる費用は、申述人一人あたり収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代(裁判所によって金額が異なります)程度です。
相続放棄に関する注意点とよくある質問
相続放棄を検討・実行するにあたって、いくつか注意すべき点があります。
注意点1:一度放棄すると原則撤回できない
相続放棄は、原則として家庭裁判所に受理された後は撤回することができません。「やっぱり財産がたくさんあったから相続したい」と思っても、基本的には認められません。だからこそ、事前の十分な調査と慎重な判断が不可欠なのです。
注意点2:次順位の相続人への影響
前述の通り、あなたが相続放棄することで、相続権は次順位の相続人に移ります。特に故人に借金がある場合、あなたが放棄することでその借金が他の親族にいってしまうことになります。トラブルを避けるためにも、事前に次順位の相続人に連絡し、状況を説明し、可能であれば共に放棄の手続きを検討するのが望ましいでしょう。
注意点3:生命保険金や死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合、多くは相続財産ではなく、受取人固有の財産とみなされます。したがって、相続放棄をしても、これらの保険金や退職金を受け取れる場合があります。(ただし、契約内容によっては相続財産となるケースもありますので、保険会社や勤務先に確認が必要です。)
注意点4:不動産について
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産となった不動産は、最終的に相続財産清算人によって管理・処分されることになります。しかし、清算人が選任されるまでは、誰も管理する人がいない「管理不全の土地・建物」となり、近隣に迷惑をかけたり、固定資産税がかかり続けたりする可能性があります。相続放棄したとしても、次順位の相続人がいない場合などは、例外的に管理責任が問われる可能性もゼロではありません(民法改正により、一定の場合に相続放棄した者が管理義務を負うケースが追加されました)。不動産が含まれる場合は、特に慎重な判断が必要です。
注意点5:3ヶ月を過ぎてから借金が判明した場合
原則として3ヶ月を過ぎると単純承認とみなされますが、例外的に、「熟慮期間中に相続財産(特に借金)があることを全く知らず、かつ知らなかったことにやむを得ない理由がある場合」などには、3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められる可能性があります。しかし、これはかなりハードルが高く、それを証明する必要があります。まずは速やかに弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。
困ったら専門家へ相談を!
相続財産の調査や評価、必要書類の収集、複雑な親族関係が絡む場合など、相続放棄の手続きは専門的な知識が必要となる場面が多くあります。また、3ヶ月という短い期間の中で正確な判断と手続きを行うのは、精神的にも大きな負担となります。
このような場合は、相続の専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
- 弁護士:相続財産の調査、借金の調査や債権者との交渉、他の相続人との間のトラブル対応、熟慮期間延長の申し立て、3ヶ月経過後の相続放棄の相談など、幅広い対応が可能です。
- 司法書士:相続放棄申述書の作成や家庭裁判所への提出手続きの代行など、書類作成や手続きの専門家です。弁護士に比べて費用が抑えられるケースが多いです。
特に借金が多い場合や、相続人が多数いる場合、行方不明の相続人がいる場合などは、専門家のサポートが不可欠です。早めに相談することで、焦らず、正確な手続きを進めることができます。
まとめ:相続放棄は「知って、調べて、判断する」ことが重要
相続は、故人から引き継ぐ大切なものですが、時に予期せぬ負担を伴うこともあります。特に借金の存在は、相続人にとって非常に大きな問題となり得ます。
相続放棄は、そうしたリスクから自分自身や家族を守るための、法律で認められた重要な手段です。
しかし、その判断と手続きには、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳しい期限があり、「法定単純承認」という落とし穴も存在します。
重要なのは、
- 「相続放棄」という選択肢があることを知る
- 故人のプラス・マイナス両方の財産を正確に調査する
- 3ヶ月の期間内に慎重に判断する
- 迷ったり、複雑な場合は速やかに専門家(弁護士・司法書士)に相談する
ということです。
この情報が、あなたが相続の状況を理解し、適切な判断を行うための一助となれば幸いです。終活は、ご自身の最期を準備するだけでなく、残されるご家族が困らないように準備することでもあります。相続について正しい知識を持つことは、ご自身の終活においても、また大切な方を亡くされた後の手続きにおいても、必ず役に立つはずです。
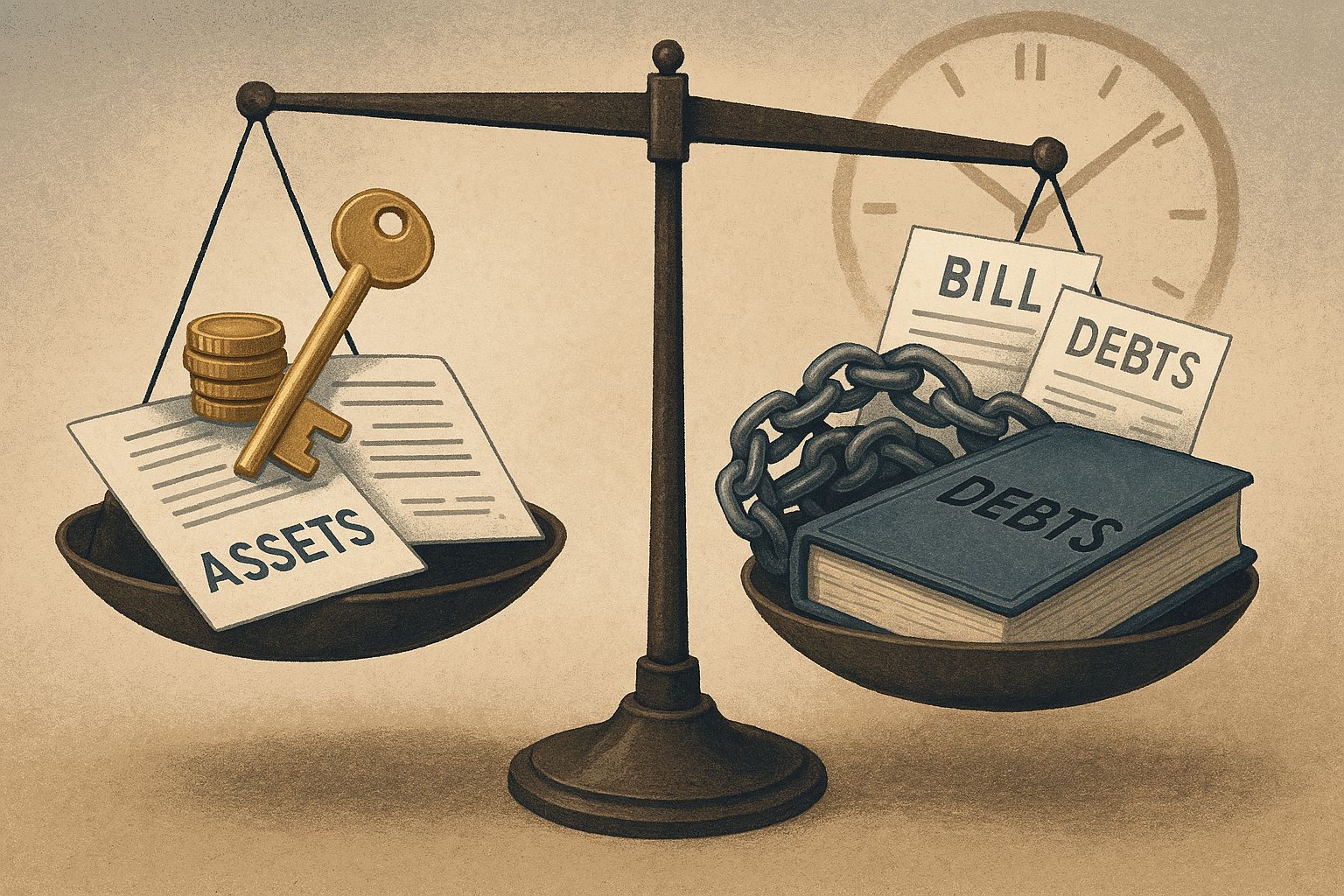


コメント